【インタビュー】VRはまだまだこれから、鍵は家庭用とアーケードの両輪展開にあり…原田氏、玉置氏に聞くBNEのバーチャルリアリティ【後編】
『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム』、『アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション』とPlayStationVRのローンチ時に、2本のタイトルをリリースしたバンダイナムコエンターテイメント。6月1日には人気格闘ゲーム『鉄拳7』においてもVRモードを搭載し、『サマーレッスン』は、アリソン・スノウ、新城ちさとという新たなキャラクターたちがラインナップに並んでいる。
また2016年、お台場に登場した「VR ZONE」は約半年間で37,000人もの来場者があり、今夏より新宿に以前の何倍もの規模の施設をオープンさせている。VRについては、家庭用と専用の筐体を使ったアーケードという2軸で多いに体験者を楽しませてくれる同社だが、VRでの開発に至るまでは非常に多くの苦労があったようだ。
本稿では、バンダイナムコ エンターテイメントグローバル事業推進室 グローバルマーケティング部ゼネラルマネージャーの原田 勝弘 氏とCS事業部 第2制作宣伝部 の玉置 絢 氏にインタビューを実施。VR開発に至るまでの挫折の連続、明らかになる世代間ギャップ、今後のバーチャルリアリティについて、包み隠す所なくお話いただいた後編となる。
![]()
株式会社バンダイナムコ エンターテイメント
グローバル事業推進室 グローバルマーケティング部
ゼネラルマネージャー
チーフプロデューサー/ゲームディレクター
原田 勝弘 氏 (写真右)
CS事業部
第2制作宣伝部
1986年生まれ
玉置 絢 氏 (写真左)
ーー『サマーレッスン』を作られていて感じた事を教えてください。
玉置:『サマーレッスン』の一番のポイントは、キャラクターが近いということです。キャラクターが本当に目の前にいるということは凄く新しいことで、そういった新しい体験がVRにはあるという事をいち早く発見できたのが、『サマーレッスン』が話題になったポイントの1つだと思っています。
原田と2人でVRをやっていた当初はそれに気づいてなかったんです。色々なVRを見ていく中で、「360度空間が広がってるって事よりも、目の前にあるものの本物感が凄い」ってことが分かったんです。ここに何かあるはずだと思って、キャラクターが近くまで来て会話したり、手を伸ばしてきたり、距離感・接近をすごく大事にして突き詰めようって決めたのが、良かったんだと思います。
私達が凄くラッキーだったのは、『鉄拳』や『ソウルキャリバー』といった作品があり、もともと3Dキャラクターの表現に関してすごく造詣が深かった。力を入れるべき勘所が分かっていたので、失敗しなかったという点もあります。
そして体験が大事なんだっていうところに注意ができたのは、BNEが「体験を商売にしたっていいじゃないか」という文化が持っていたことですね。特にアミューズメント出身の人はゲームであることにこだわっていない人が多いんです。トータルの体験で自分たちはお金をもらってるという風土もありました。
原田:『鉄拳』は、格ゲーを作るために作ったってよく言われるんです。ただ、元々はそうじゃなくて、人体制御に重きを置いていたゲームです。ポリゴン黎明期で、将来これは絶対に使われる技術であって、複数の人間をどう動かすか、一体のキャラクターのアニメーションや肌をどうリアルに表現するかというのはすごく大きいテーマのひとつだった。
ただ、そういったベテランはいたのですが、最初のひかりちゃんのゲームモデルは全然だめだったんですね。レンズの歪みや画角の問題もありましたし、近づいた時とか興奮・臨場感ではなく、ムカつきの方が先にきました。腹が立つんですね、こいつは一体なんだろうと。
僕らのゲームの論法は、デフォルメでした。ゲームは何回か歴史を繰り返しているんですが、まずはドット絵で始まり、色がない表現。するとデフォルメするしかない。多くの色が使えるようになって繊細な表現になったけど、ポリゴンの時代でリセットされてしまった。
当初はテクスチャ表現も荒いので、またデフォルメに戻って、何でも大げさになります。眉毛が太く、動きは大きく、大げさにしないとキャラが見えないんです。造形もポリゴン黎明期はとにかくデフォルメ。VRがすごく繊細だと思ったのは、眉毛を大げさにするとキャラクターの顔ひとつとっても、何か凄い違和感を感じる。「こいつ俺を馬鹿にしてるんじゃないか?」っていう(笑)。
表情の作り方やモデルのバランスもVR用に作る必要があります。この時に「表現手法が変わる時代になっちゃったな」っていうのをすごく思いました。だから、現実を改めて見直すいつようが出てきて、今までと全く違うアプローチなので、正直戸惑いはありましたね。
![]()
玉置:人間がフィクションを作っていく中で、貯めてきたノウハウは、記号化して物事を面白く伝えるにはすごく向いています。現実から離れていても、それを理解できるという共通認識を人間が持ってるから成立する話です。でも、VRのような本当の世界を表現して、その世界の中にプレイヤーも入っていくというレベルに来ると、それは単純に嘘と思えてしまうですね。
また、モーションキャプチャする人も普通、映画や演劇などの演者といった感覚で振る舞います。カメラが遠かったり、観客が遠かったりしても、自分がどういう表情をしているかわかるように必ずオーバーに演技をします。それもVRの中で見ると違和感があるのです。VRでは本当に目の前にいるので。
ただ、逆に本当の現実をコピーして終わりにすると、今度は面白くないんです。可愛かったり、魅力的だったり、面白かったりするためにはフィクション性も必要です。
そのフィクションとリアルの配合という部分において非常に悩みましたし、その配分の振り分け方のコツこそが『サマーレッスン』の秘密になります。
当時は機材もなかったですからね。今VRで 一旗揚げようっていう人には信じられないと思うんですが、顔が可愛くなかった最初の理由はただVR の機材がなかったからなんです。当時VRの機材がどの会社もまだ作ってる段階で手元にないんです。
原田:全員で1台しかなかったですよ。
玉置:今では考えられませんが、普通のモニターで作っていました。画面でキャラクターを作ってもVR の中で見た印象が違うんです。ビジュアルアーティストの人が、普段は凄くかわいいキャラクターを作るのに、どうしても歪んでしまう。
機材がだんだん増えてきて、皆がHMDを被れるようになって、思い通りのものが作れるようになってきました。戦後まもない日本みたいな状況でしたね。物がない、やり方もわからないみたいな。
原田:今、みんな恵まれてると思いますよ。今までのモデルは、皆で同じモニターを見て話ができたんですが、当時はHMDをつけて、「ここが違う。ここをもっとこうして!」なんて言っても、僕がどこを指してるかもわからない。言ったことがリアルタイムに伝わらない。プレゼンの弱さと全く一緒のことが、開発現場でも起きるんですね。
玉置:そのあと、SIE(旧 Sony Computer Entertainment) JAPAN Studio ASOBI! Team さんという研究チームが、コントローラをVR空間に出せるデモを2015年のE3で発表しました。そして『ダンガンロンパVR』の体験版でも、コントローラから出るビームで何かを指示するっていうギミックが出てきたりして、そのデモを見て「これ開発で使える」って話になったんです。この仕組みが流行った頃からようやく、「ここが、おかしい」と言えるようになりました。
原田:プログラマも昔はモニターでエディタを見ながら制作してたんですが、エディター画面を自分のVR HMDの中で出せるようにしたんです。VRのゲームをVR上で作れるようにしました(笑)
玉置:その制作環境はすごいモチベーションが上がるみたいですよ(笑)
原田:これはすごい未来感ですよ。プログラマがヘッドマウントディスプレイをしたままキーボード作業している光景。
ただ、ベテランの人たちが培ってきたものがあるからこそ、早く対応できている部分と、今までの経験が役に立たない部分。モデルだとアニメーションの作り方を変えないと行けなくなってしまった。
何よりもショックを受けたのは「カメラ」を奪われることで、ゲーム業界にとって恐ろしいことだと思ったんです。ゲームはカメラでほとんど支配されていて、そこでルールが決められている。縦スクロールゲームは縦に上から勝手にカメラを見せられている状態です。進行方向から何からカメラによって決められているんです。
FPSは自由だって言いますが、見せたい映像だとか見せたい演出やシナリオはカメラ固定だったりして強制で向けられます。エイミングという要素だけが自由になる部分です。でもVRで未だに課題だと思うのは、カメラをユーザーに全部委ねる点です。カメラが強制だったら当然めまいや酔いを誘発してしまう。昔あったカメラを中心とした演出やおもしろさは、変わってしまうんだろうなって思います。
![]()
ーー見せたくないものも、見られてしまうようなケースも出てしまいます
原田:それは隠しようの問題で、まだ何とかなるかもしれないですね。例えばバイオハザードでは、今までのバイオハザードだから、良い意味でのユーザーへの刷り込みかパターンがあって、かなり怖く出来てて面白いです。
ただ今までの論法でVRでは人によって「あのシーン怖かった」がブレる可能性があるんです。そうすると確実に今まで起こせていた名場面みたいなものがなくなってくる事も考慮する必要がありますね。
ある場面で、ドアがギィーって開いて、恐ろしい少女が覗いているというシチュエーションなのに、VRだとプレイヤーが全然関係ないものを注視してて、見てもらえない可能性がある。一旦は現れたた恐ろしい少女キャラクターはプレイヤーの視線フラグが立つまで、健気にずっとこっちを見て待ってることを想像するとシュール過ぎるでしょう(笑)。
玉置:ゲームをインタラクティブなストーリーだと考えると、結局ストーリーテリングの範疇なんです。ですが、VRが提供するのは体験なんです。体験とインタラクティブなストーリーが全く同じ意味かというと、そうではない。ストーリーは現実の中で何を切り取ってフォーカスして並べるかっていうことです。体験は全部をひっくるめて体験なので何も切り取れないですね。つまりフィクションのような演出ができないんです。
ストーリーに寄せすぎると強制力が強すぎて、VRの体験をした感じにはならない。本当に生の体験だけをやると、今度何を見せたいコンテンツなのかが全く伝わらない。この間の問題をどう解決していくかすごく難しいです。
まだ『サマーレッスン』が割と楽だったのは、自然の中を観光や遊園地といったアクティビティやアトラクションと同じで、人間が案内するということです。人は、人間に呼びかけられたり、人間が指差したりするとつい付き合っちゃうんですね。それは強制力としては心地良いですし、人に何かを意識喚起されることは、ついつい従っちゃうんです。
これが『サマーレッスン』はキャラクターが存在するものだから、まだ出来ています。キャラクターがいないVRゲームは大変だと思います。そういう案内役がいるだけでキャラクターは有利だと思いますね。文字で出すのも無粋ですし。
原田:まだまだそういう意味では、発見の余地があるんだと思います。
玉置:ちょうどこの間、『狼と香辛料』というライトノベルの作家 支倉凍砂さんとお話したんです。支倉先生は、SteamでVRアニメ『Project Lux』をリリースされました。支倉先生には、『サマーレッスン』を発売前に見せたことがあるんです。
先生も、まさにストーリーテリングをVRでどう扱うか?ということを考えておられて、『Project Lux』はある意味その一つの答えなのだろうと思います。『サマーレッスン』とは、考え方が全然違うのがポイントですね。
あと、その時に話した別のVR作者さんの話もあります。それはVRなのに演劇ものなんです。自分が演劇の中の役者で、ストーリーに合わせて演技をすると話が進む仕組みになっています。これなら、自分はストーリーを体感しつつ、舞台役者だからやっているというシチュエーションなので、体験の阻害にもならない。
これうまいこと考えたなと思ったんですね。こんな感じでいろんな人が、いろんな考え方をしている。支倉先生の考え方も演劇型VRを作った人も違うと思います。どんどんいろんな考え方が出て行く。『サマーレッスン』は一つの土台というか、型にしか過ぎないんだなと。ただそんな中で割とメジャーな1つの型になれたのは嬉しいと思います。
![]()
ーー今後のVR領域の展望を聞かせてください
玉置:私はキャラクターがVRにおいては、単にキャラクターと交流できて楽しい・嬉しいっていうところで、まず大きな市場があると思っています。
今はVRのハードウェアの普及度合いに影響を受けていて、どうしてもゲームっぽいもの多いです。『サマーレッスン』がゲームというジャンルになっているのは、お客様に得体の知れないものだと思って欲しくなかったからなんです。
ちょっと育成ゲーム的な要素があるのは、ゲームに慣れている我々プレイヤーが、拒否感なく受け入れられるようにするためのものです。
わかりやすく世の中に受け入れられるために、そういうものからスタートするのが定石かなと思うんです。そして、ゲームが好きな人から多くの人へと普及していき、どんどん広がっていってVRをみんなが手に取るような状況になれば、キャラクター物の分野にもすごく大きな市場があるのではないかと予測しています。
自分の好きな人・キャラクターと一緒の空間にいられるとか、会話ができて、新たな一面を掘って知っていくことができる。それが楽しいっていう。しかもそれだけではなくて、先ほどお話したように、VR におけるキャラクターという役割は、ただコンテンツであるだけではなく、ナビゲーションとして、どんなVRコンテンツでも使える道具としても成り立つわけです。
人間より優れたインターフェースはないですし、対話型インターフェースと言ったり、Windows の画面をダイアログって言いますけど、UI の歴史を遡ると、もともと基本の考え方は対話なんですね。人間と人間で会話をするっていう行為を模倣することが、一番のインターフェイスなんです。現実でも一緒で、機械で操作するところよりかは、ホテルのフロントは人がいるところの方がいいし、人間がいることが1番高度なインターフェイスだなと思います。
キャラクターとの会話を、マン・マシン・インターフェイスの一種だって考えると、そういうの方向でまだまだ未来があります。キャラクター物っていうのは、ただ単にコンテンツではなくて、VR をより高度な技術 にしていくために必要なものだということが分かります。例えば、XVIの近藤さん(Goroman氏)がやっている『Mikulus』は、VR 上のデスクトップアプリで、キャラクターが登場しているんですけど、まさにそういうのに向かっていくVRキャラクターって、単なるストーリーテリングの登場人物とか、そういうものだけの役割ではないってことを示してくれる良い例だと思います。
原田:僕はVRに対して、今考え方・見方がちょっと変わってきていて、玉置などの若い世代にVR を託しているんです。いち早くVRをやってきていて、いろんなゲームを試していたりしたせいで、ゲーム部門とVRそのものっていうのはと求められるペースが違うなと思ったんです。
例えば今VRは、医療やトラウマを治すといった分野にも使われ始めてきて、実生活の部分で活用できると思います。一方、ゲームが凄く贅沢だなと思うのは、ハードウェアの革新があったからこそ。「これやりたい」っていうのでソフトに色々なアイディアが出てきて、今でも模索段階です。
ただ僕の中ではソフトウェアでやっていきたいこと、表現できることに対してハードウェアの頭打ちが思ったよりも来たかなと思っているんです。まだ体験できていない人がいることも承知しています。でもハードウェアの進化はもっともっと早く進んでほしい。
もう今はVRゲームを体験しすぎて、プレビューで恐らくこういう体験だろう、というのがわかってしまうんですね。そうすると装着する手間、面倒臭さが僕の中で目立ってきてしまった。これは逆に言えば、この装着の手間の問題を解決すると、すごく普及する可能性があるということでもある。その面倒臭さを超えるハードウェアの進化を待ち望んでいます。
ゲームソフト屋は頭の中でゲームを作ります。なので想像力がハードウェアを追い越していることは昔からあるのですが、それでも凄いテクノロジやハードウェアが先に出てきたんで興奮し、そこから生まれたゲームやアイデアも多々ある。VRに関しては既にみんなの想像力が先に行き始めてるんじゃないかと思います。
少なくとも僕は今そのフェーズで、ハードウェアの進化待ちなんです。VRはまだまだ研究分野としては生活に活用できるところがありつつも、エンターテイメントの分野では想像力が追いつき、追い越し始めたので、ハードウェアの進化を1回2回とどんどんと早く来て欲しいと思っている人は多いんじゃないかな?
ネガティブに聞こえてしまうのですが、まったく逆で、この分野にはもっともっと先がある、面白い未来があるんだよと言いたいわけです。この加速をなんとか早めたいなって思いますね。僕個人の力ではどうにもならない事が多いけど。
玉置:今、そう感じている方も多いかと思います。VRに携わる人が増えて色んな集会が増えました。2016年でVR 元年でしたが、2017年に入ってきて、VR に詳しい人はVR に慣れてきている。なのにVRをまだ触ったことない人もいるという、かなりいびつな状況になっています。
VRに慣れすぎたのでMR に行くという人が多いですが、そういう傾向がVR専門家に見られるのは、かなり先を見ているからだと思います。だから今は、掘り下げすぎた人と、やったことのない人の差がものすごいある。
原田:僕はハードウェアの進化待ちですが、先にやりすぎた人、そこを埋めるものだなって思ったのはアーケードかなと思っています。色々な仕掛けがある筐体で体験するフィジカルなVRは時代を繋ぐことが出来ると思っています。
僕、"VR"に興味があるので、基本的にはどこかに移動すること自体が嫌なんですが、VR施設に行ってしまえばディズニーランドと一緒でその気になるんです。その環境の時点で、普段の家庭のVR環境と違います。スキーで寒い風が来て震えて、揺れて傾くとか。ロボットに乗って動くっていう体験。あれは未だに最先端を行き過ぎてる人でも、初めての人でも喜べるVR体験だと思いますし、時代を繋ぐのにフィットしているやり方だなと。
玉置:それで言うと我々は家庭用・アーケードに関わるラッキーなところにいます。アーケードも一つの市場になっていて、最先端のものが見たいとか、今までにないものですとか、いろんなエンターテイメントを知り尽くしている人の飽きに対しての特効薬になる。
いろんなエンターテイメントの中でもアーケードだけは飽きずに新鮮でいられます。
![]()
原田:人間って贅沢だなと思いますよ。携帯電話も最初出た時は離れたところでも繋がる。なんて便利なんだろうと。もっときれいな画面だとか、インターネットが欲しいから始まって、ゲームがしたい、映画が見たい、それと一緒です。
VRでの表現はある程度のポリゴン数が必要で、ハードウェアのスペックがずっと足りなかった。今ようやく性能が追いつたからこそVR HMD時代がやってきた。
ただ、2016年はVR元年って言ってたのに、もうスペックが足りないって言い始めてますね(笑)
玉置:今は本当に正念場だと思うんです。飽きてる人に合わせてどんどん高度なVRネタだけを突き詰めていってしまうと、VR村が出来上がって、マニアックな一部の人達だけのエンターテイメントになってしまいます。それは良くないですね。
「あの人、テレビ好きそうだよね」って言う人はいないと思うんです。それはテレビが一部の人だけのエンターテイメントではないからですね。
でも「あの人、VR好きそうだよね」という言葉はどこでも見られますし、テレビが辿ったような一般化の道筋を目指さないと、VR は未来永劫「好きそうな人と、よく知らない人がいる」という趣味のものになる危険があって、実際、今、そうなりかけているとも思えます。
だから、最先端にいる人も、未経験の人もどちらもフォローしなければいけない。それは業界の課題だと思います。
飽きてしまった人の期待に答えながら、まだ未経験の人に対しても提供するという2軸が大事なんです。しかし、参戦してくださるメーカーさんはまだまだ少ないんですよね。
もちろんプレゼンするのがすごく難しいので、二の足を踏むのはわかります。でも「今のゲームだけを作り続けて、業界が残ると思うのか」というところで考えてみれば、何でも手を出してみなければいけないのではないでしょうか。
まだVRの楽しさにはまりきっていない人に向けて、家庭用のチャンネルでVRを提供するのも、飽きてる人に対して斬新なアイディアを、アトラクションのチャンネルで供給することも、業界全体でやるべきだと思います。
原田:『サマーレッスン』は、まだまだ展開中です初めてのVRとしては、絶対感じるものがあります。僕は他社から売れるゲームが出てくると、焦燥感を得たり、嫉妬すると嫌味の一つも言いたくなるんですが、VRってまだそういうゲームが少ないと思っています。「やられた!ちくしょう!」っていうような盛り上がり方がしたいです(笑)
業界的にはみんなが嫉妬するようなコンテンツが出てきてほしいなって思います。
玉置:元年に乗り遅れて手を出さなかったから、やらないというのは、もったいないです。むしろこれからがチャンスです。基本的な勝ち筋というのが見えてきて、それに対してどうやってカウンターを当てるかを考えられる時期というのは市場として、1番新規参入がしやすいはずで、もっとも盛り上がればいいなと思っています。
ーーありがとうございました。
(編集・聞き手:ドラゴン・リバー)
(取材・文・撮影 : 編集部 和田和也)
また2016年、お台場に登場した「VR ZONE」は約半年間で37,000人もの来場者があり、今夏より新宿に以前の何倍もの規模の施設をオープンさせている。VRについては、家庭用と専用の筐体を使ったアーケードという2軸で多いに体験者を楽しませてくれる同社だが、VRでの開発に至るまでは非常に多くの苦労があったようだ。
本稿では、バンダイナムコ エンターテイメントグローバル事業推進室 グローバルマーケティング部ゼネラルマネージャーの原田 勝弘 氏とCS事業部 第2制作宣伝部 の玉置 絢 氏にインタビューを実施。VR開発に至るまでの挫折の連続、明らかになる世代間ギャップ、今後のバーチャルリアリティについて、包み隠す所なくお話いただいた後編となる。

■大げさだと腹が立つ、VRにおけるリアル世界の配合とは?
株式会社バンダイナムコ エンターテイメント
グローバル事業推進室 グローバルマーケティング部
ゼネラルマネージャー
チーフプロデューサー/ゲームディレクター
原田 勝弘 氏 (写真右)
CS事業部
第2制作宣伝部
1986年生まれ
玉置 絢 氏 (写真左)
ーー『サマーレッスン』を作られていて感じた事を教えてください。
玉置:『サマーレッスン』の一番のポイントは、キャラクターが近いということです。キャラクターが本当に目の前にいるということは凄く新しいことで、そういった新しい体験がVRにはあるという事をいち早く発見できたのが、『サマーレッスン』が話題になったポイントの1つだと思っています。
原田と2人でVRをやっていた当初はそれに気づいてなかったんです。色々なVRを見ていく中で、「360度空間が広がってるって事よりも、目の前にあるものの本物感が凄い」ってことが分かったんです。ここに何かあるはずだと思って、キャラクターが近くまで来て会話したり、手を伸ばしてきたり、距離感・接近をすごく大事にして突き詰めようって決めたのが、良かったんだと思います。
私達が凄くラッキーだったのは、『鉄拳』や『ソウルキャリバー』といった作品があり、もともと3Dキャラクターの表現に関してすごく造詣が深かった。力を入れるべき勘所が分かっていたので、失敗しなかったという点もあります。
そして体験が大事なんだっていうところに注意ができたのは、BNEが「体験を商売にしたっていいじゃないか」という文化が持っていたことですね。特にアミューズメント出身の人はゲームであることにこだわっていない人が多いんです。トータルの体験で自分たちはお金をもらってるという風土もありました。
原田:『鉄拳』は、格ゲーを作るために作ったってよく言われるんです。ただ、元々はそうじゃなくて、人体制御に重きを置いていたゲームです。ポリゴン黎明期で、将来これは絶対に使われる技術であって、複数の人間をどう動かすか、一体のキャラクターのアニメーションや肌をどうリアルに表現するかというのはすごく大きいテーマのひとつだった。
ただ、そういったベテランはいたのですが、最初のひかりちゃんのゲームモデルは全然だめだったんですね。レンズの歪みや画角の問題もありましたし、近づいた時とか興奮・臨場感ではなく、ムカつきの方が先にきました。腹が立つんですね、こいつは一体なんだろうと。
僕らのゲームの論法は、デフォルメでした。ゲームは何回か歴史を繰り返しているんですが、まずはドット絵で始まり、色がない表現。するとデフォルメするしかない。多くの色が使えるようになって繊細な表現になったけど、ポリゴンの時代でリセットされてしまった。
当初はテクスチャ表現も荒いので、またデフォルメに戻って、何でも大げさになります。眉毛が太く、動きは大きく、大げさにしないとキャラが見えないんです。造形もポリゴン黎明期はとにかくデフォルメ。VRがすごく繊細だと思ったのは、眉毛を大げさにするとキャラクターの顔ひとつとっても、何か凄い違和感を感じる。「こいつ俺を馬鹿にしてるんじゃないか?」っていう(笑)。
表情の作り方やモデルのバランスもVR用に作る必要があります。この時に「表現手法が変わる時代になっちゃったな」っていうのをすごく思いました。だから、現実を改めて見直すいつようが出てきて、今までと全く違うアプローチなので、正直戸惑いはありましたね。

玉置:人間がフィクションを作っていく中で、貯めてきたノウハウは、記号化して物事を面白く伝えるにはすごく向いています。現実から離れていても、それを理解できるという共通認識を人間が持ってるから成立する話です。でも、VRのような本当の世界を表現して、その世界の中にプレイヤーも入っていくというレベルに来ると、それは単純に嘘と思えてしまうですね。
また、モーションキャプチャする人も普通、映画や演劇などの演者といった感覚で振る舞います。カメラが遠かったり、観客が遠かったりしても、自分がどういう表情をしているかわかるように必ずオーバーに演技をします。それもVRの中で見ると違和感があるのです。VRでは本当に目の前にいるので。
ただ、逆に本当の現実をコピーして終わりにすると、今度は面白くないんです。可愛かったり、魅力的だったり、面白かったりするためにはフィクション性も必要です。
そのフィクションとリアルの配合という部分において非常に悩みましたし、その配分の振り分け方のコツこそが『サマーレッスン』の秘密になります。
当時は機材もなかったですからね。今VRで 一旗揚げようっていう人には信じられないと思うんですが、顔が可愛くなかった最初の理由はただVR の機材がなかったからなんです。当時VRの機材がどの会社もまだ作ってる段階で手元にないんです。
原田:全員で1台しかなかったですよ。
玉置:今では考えられませんが、普通のモニターで作っていました。画面でキャラクターを作ってもVR の中で見た印象が違うんです。ビジュアルアーティストの人が、普段は凄くかわいいキャラクターを作るのに、どうしても歪んでしまう。
機材がだんだん増えてきて、皆がHMDを被れるようになって、思い通りのものが作れるようになってきました。戦後まもない日本みたいな状況でしたね。物がない、やり方もわからないみたいな。
原田:今、みんな恵まれてると思いますよ。今までのモデルは、皆で同じモニターを見て話ができたんですが、当時はHMDをつけて、「ここが違う。ここをもっとこうして!」なんて言っても、僕がどこを指してるかもわからない。言ったことがリアルタイムに伝わらない。プレゼンの弱さと全く一緒のことが、開発現場でも起きるんですね。
玉置:そのあと、SIE(旧 Sony Computer Entertainment) JAPAN Studio ASOBI! Team さんという研究チームが、コントローラをVR空間に出せるデモを2015年のE3で発表しました。そして『ダンガンロンパVR』の体験版でも、コントローラから出るビームで何かを指示するっていうギミックが出てきたりして、そのデモを見て「これ開発で使える」って話になったんです。この仕組みが流行った頃からようやく、「ここが、おかしい」と言えるようになりました。
原田:プログラマも昔はモニターでエディタを見ながら制作してたんですが、エディター画面を自分のVR HMDの中で出せるようにしたんです。VRのゲームをVR上で作れるようにしました(笑)
玉置:その制作環境はすごいモチベーションが上がるみたいですよ(笑)
原田:これはすごい未来感ですよ。プログラマがヘッドマウントディスプレイをしたままキーボード作業している光景。
ただ、ベテランの人たちが培ってきたものがあるからこそ、早く対応できている部分と、今までの経験が役に立たない部分。モデルだとアニメーションの作り方を変えないと行けなくなってしまった。
何よりもショックを受けたのは「カメラ」を奪われることで、ゲーム業界にとって恐ろしいことだと思ったんです。ゲームはカメラでほとんど支配されていて、そこでルールが決められている。縦スクロールゲームは縦に上から勝手にカメラを見せられている状態です。進行方向から何からカメラによって決められているんです。
FPSは自由だって言いますが、見せたい映像だとか見せたい演出やシナリオはカメラ固定だったりして強制で向けられます。エイミングという要素だけが自由になる部分です。でもVRで未だに課題だと思うのは、カメラをユーザーに全部委ねる点です。カメラが強制だったら当然めまいや酔いを誘発してしまう。昔あったカメラを中心とした演出やおもしろさは、変わってしまうんだろうなって思います。

ーー見せたくないものも、見られてしまうようなケースも出てしまいます
原田:それは隠しようの問題で、まだ何とかなるかもしれないですね。例えばバイオハザードでは、今までのバイオハザードだから、良い意味でのユーザーへの刷り込みかパターンがあって、かなり怖く出来てて面白いです。
ただ今までの論法でVRでは人によって「あのシーン怖かった」がブレる可能性があるんです。そうすると確実に今まで起こせていた名場面みたいなものがなくなってくる事も考慮する必要がありますね。
ある場面で、ドアがギィーって開いて、恐ろしい少女が覗いているというシチュエーションなのに、VRだとプレイヤーが全然関係ないものを注視してて、見てもらえない可能性がある。一旦は現れたた恐ろしい少女キャラクターはプレイヤーの視線フラグが立つまで、健気にずっとこっちを見て待ってることを想像するとシュール過ぎるでしょう(笑)。
玉置:ゲームをインタラクティブなストーリーだと考えると、結局ストーリーテリングの範疇なんです。ですが、VRが提供するのは体験なんです。体験とインタラクティブなストーリーが全く同じ意味かというと、そうではない。ストーリーは現実の中で何を切り取ってフォーカスして並べるかっていうことです。体験は全部をひっくるめて体験なので何も切り取れないですね。つまりフィクションのような演出ができないんです。
ストーリーに寄せすぎると強制力が強すぎて、VRの体験をした感じにはならない。本当に生の体験だけをやると、今度何を見せたいコンテンツなのかが全く伝わらない。この間の問題をどう解決していくかすごく難しいです。
まだ『サマーレッスン』が割と楽だったのは、自然の中を観光や遊園地といったアクティビティやアトラクションと同じで、人間が案内するということです。人は、人間に呼びかけられたり、人間が指差したりするとつい付き合っちゃうんですね。それは強制力としては心地良いですし、人に何かを意識喚起されることは、ついつい従っちゃうんです。
これが『サマーレッスン』はキャラクターが存在するものだから、まだ出来ています。キャラクターがいないVRゲームは大変だと思います。そういう案内役がいるだけでキャラクターは有利だと思いますね。文字で出すのも無粋ですし。
原田:まだまだそういう意味では、発見の余地があるんだと思います。
玉置:ちょうどこの間、『狼と香辛料』というライトノベルの作家 支倉凍砂さんとお話したんです。支倉先生は、SteamでVRアニメ『Project Lux』をリリースされました。支倉先生には、『サマーレッスン』を発売前に見せたことがあるんです。
先生も、まさにストーリーテリングをVRでどう扱うか?ということを考えておられて、『Project Lux』はある意味その一つの答えなのだろうと思います。『サマーレッスン』とは、考え方が全然違うのがポイントですね。
あと、その時に話した別のVR作者さんの話もあります。それはVRなのに演劇ものなんです。自分が演劇の中の役者で、ストーリーに合わせて演技をすると話が進む仕組みになっています。これなら、自分はストーリーを体感しつつ、舞台役者だからやっているというシチュエーションなので、体験の阻害にもならない。
これうまいこと考えたなと思ったんですね。こんな感じでいろんな人が、いろんな考え方をしている。支倉先生の考え方も演劇型VRを作った人も違うと思います。どんどんいろんな考え方が出て行く。『サマーレッスン』は一つの土台というか、型にしか過ぎないんだなと。ただそんな中で割とメジャーな1つの型になれたのは嬉しいと思います。
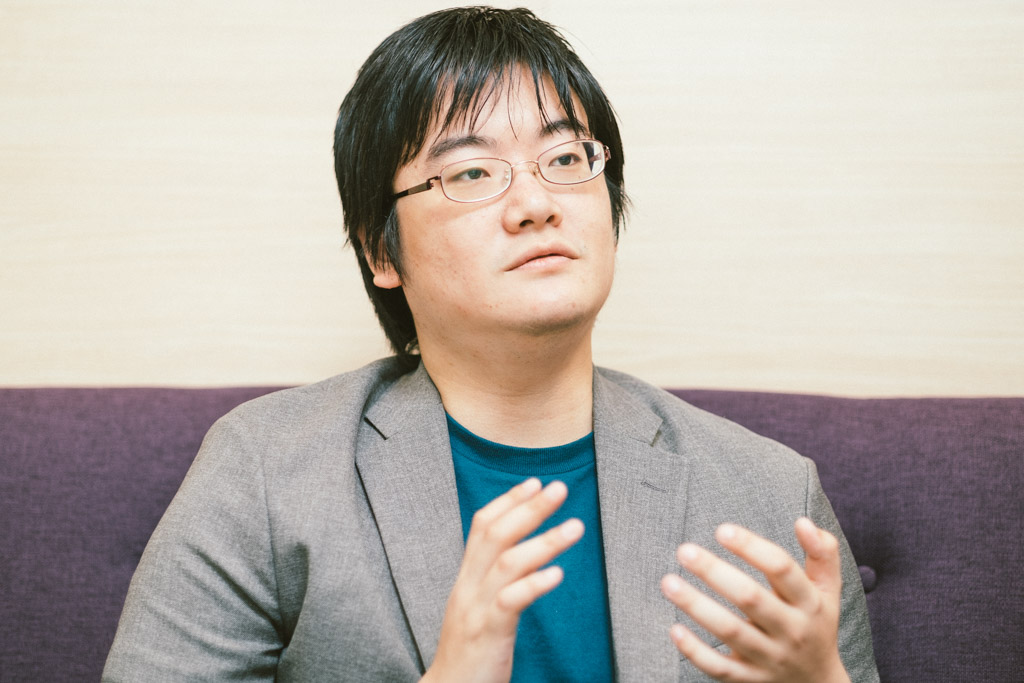
■閉鎖的なVR村にならないように
ーー今後のVR領域の展望を聞かせてください
玉置:私はキャラクターがVRにおいては、単にキャラクターと交流できて楽しい・嬉しいっていうところで、まず大きな市場があると思っています。
今はVRのハードウェアの普及度合いに影響を受けていて、どうしてもゲームっぽいもの多いです。『サマーレッスン』がゲームというジャンルになっているのは、お客様に得体の知れないものだと思って欲しくなかったからなんです。
ちょっと育成ゲーム的な要素があるのは、ゲームに慣れている我々プレイヤーが、拒否感なく受け入れられるようにするためのものです。
わかりやすく世の中に受け入れられるために、そういうものからスタートするのが定石かなと思うんです。そして、ゲームが好きな人から多くの人へと普及していき、どんどん広がっていってVRをみんなが手に取るような状況になれば、キャラクター物の分野にもすごく大きな市場があるのではないかと予測しています。
自分の好きな人・キャラクターと一緒の空間にいられるとか、会話ができて、新たな一面を掘って知っていくことができる。それが楽しいっていう。しかもそれだけではなくて、先ほどお話したように、VR におけるキャラクターという役割は、ただコンテンツであるだけではなく、ナビゲーションとして、どんなVRコンテンツでも使える道具としても成り立つわけです。
人間より優れたインターフェースはないですし、対話型インターフェースと言ったり、Windows の画面をダイアログって言いますけど、UI の歴史を遡ると、もともと基本の考え方は対話なんですね。人間と人間で会話をするっていう行為を模倣することが、一番のインターフェイスなんです。現実でも一緒で、機械で操作するところよりかは、ホテルのフロントは人がいるところの方がいいし、人間がいることが1番高度なインターフェイスだなと思います。
キャラクターとの会話を、マン・マシン・インターフェイスの一種だって考えると、そういうの方向でまだまだ未来があります。キャラクター物っていうのは、ただ単にコンテンツではなくて、VR をより高度な技術 にしていくために必要なものだということが分かります。例えば、XVIの近藤さん(Goroman氏)がやっている『Mikulus』は、VR 上のデスクトップアプリで、キャラクターが登場しているんですけど、まさにそういうのに向かっていくVRキャラクターって、単なるストーリーテリングの登場人物とか、そういうものだけの役割ではないってことを示してくれる良い例だと思います。
原田:僕はVRに対して、今考え方・見方がちょっと変わってきていて、玉置などの若い世代にVR を託しているんです。いち早くVRをやってきていて、いろんなゲームを試していたりしたせいで、ゲーム部門とVRそのものっていうのはと求められるペースが違うなと思ったんです。
例えば今VRは、医療やトラウマを治すといった分野にも使われ始めてきて、実生活の部分で活用できると思います。一方、ゲームが凄く贅沢だなと思うのは、ハードウェアの革新があったからこそ。「これやりたい」っていうのでソフトに色々なアイディアが出てきて、今でも模索段階です。
ただ僕の中ではソフトウェアでやっていきたいこと、表現できることに対してハードウェアの頭打ちが思ったよりも来たかなと思っているんです。まだ体験できていない人がいることも承知しています。でもハードウェアの進化はもっともっと早く進んでほしい。
もう今はVRゲームを体験しすぎて、プレビューで恐らくこういう体験だろう、というのがわかってしまうんですね。そうすると装着する手間、面倒臭さが僕の中で目立ってきてしまった。これは逆に言えば、この装着の手間の問題を解決すると、すごく普及する可能性があるということでもある。その面倒臭さを超えるハードウェアの進化を待ち望んでいます。
ゲームソフト屋は頭の中でゲームを作ります。なので想像力がハードウェアを追い越していることは昔からあるのですが、それでも凄いテクノロジやハードウェアが先に出てきたんで興奮し、そこから生まれたゲームやアイデアも多々ある。VRに関しては既にみんなの想像力が先に行き始めてるんじゃないかと思います。
少なくとも僕は今そのフェーズで、ハードウェアの進化待ちなんです。VRはまだまだ研究分野としては生活に活用できるところがありつつも、エンターテイメントの分野では想像力が追いつき、追い越し始めたので、ハードウェアの進化を1回2回とどんどんと早く来て欲しいと思っている人は多いんじゃないかな?
ネガティブに聞こえてしまうのですが、まったく逆で、この分野にはもっともっと先がある、面白い未来があるんだよと言いたいわけです。この加速をなんとか早めたいなって思いますね。僕個人の力ではどうにもならない事が多いけど。
玉置:今、そう感じている方も多いかと思います。VRに携わる人が増えて色んな集会が増えました。2016年でVR 元年でしたが、2017年に入ってきて、VR に詳しい人はVR に慣れてきている。なのにVRをまだ触ったことない人もいるという、かなりいびつな状況になっています。
VRに慣れすぎたのでMR に行くという人が多いですが、そういう傾向がVR専門家に見られるのは、かなり先を見ているからだと思います。だから今は、掘り下げすぎた人と、やったことのない人の差がものすごいある。
原田:僕はハードウェアの進化待ちですが、先にやりすぎた人、そこを埋めるものだなって思ったのはアーケードかなと思っています。色々な仕掛けがある筐体で体験するフィジカルなVRは時代を繋ぐことが出来ると思っています。
僕、"VR"に興味があるので、基本的にはどこかに移動すること自体が嫌なんですが、VR施設に行ってしまえばディズニーランドと一緒でその気になるんです。その環境の時点で、普段の家庭のVR環境と違います。スキーで寒い風が来て震えて、揺れて傾くとか。ロボットに乗って動くっていう体験。あれは未だに最先端を行き過ぎてる人でも、初めての人でも喜べるVR体験だと思いますし、時代を繋ぐのにフィットしているやり方だなと。
玉置:それで言うと我々は家庭用・アーケードに関わるラッキーなところにいます。アーケードも一つの市場になっていて、最先端のものが見たいとか、今までにないものですとか、いろんなエンターテイメントを知り尽くしている人の飽きに対しての特効薬になる。
いろんなエンターテイメントの中でもアーケードだけは飽きずに新鮮でいられます。

原田:人間って贅沢だなと思いますよ。携帯電話も最初出た時は離れたところでも繋がる。なんて便利なんだろうと。もっときれいな画面だとか、インターネットが欲しいから始まって、ゲームがしたい、映画が見たい、それと一緒です。
VRでの表現はある程度のポリゴン数が必要で、ハードウェアのスペックがずっと足りなかった。今ようやく性能が追いつたからこそVR HMD時代がやってきた。
ただ、2016年はVR元年って言ってたのに、もうスペックが足りないって言い始めてますね(笑)
玉置:今は本当に正念場だと思うんです。飽きてる人に合わせてどんどん高度なVRネタだけを突き詰めていってしまうと、VR村が出来上がって、マニアックな一部の人達だけのエンターテイメントになってしまいます。それは良くないですね。
「あの人、テレビ好きそうだよね」って言う人はいないと思うんです。それはテレビが一部の人だけのエンターテイメントではないからですね。
でも「あの人、VR好きそうだよね」という言葉はどこでも見られますし、テレビが辿ったような一般化の道筋を目指さないと、VR は未来永劫「好きそうな人と、よく知らない人がいる」という趣味のものになる危険があって、実際、今、そうなりかけているとも思えます。
だから、最先端にいる人も、未経験の人もどちらもフォローしなければいけない。それは業界の課題だと思います。
飽きてしまった人の期待に答えながら、まだ未経験の人に対しても提供するという2軸が大事なんです。しかし、参戦してくださるメーカーさんはまだまだ少ないんですよね。
もちろんプレゼンするのがすごく難しいので、二の足を踏むのはわかります。でも「今のゲームだけを作り続けて、業界が残ると思うのか」というところで考えてみれば、何でも手を出してみなければいけないのではないでしょうか。
まだVRの楽しさにはまりきっていない人に向けて、家庭用のチャンネルでVRを提供するのも、飽きてる人に対して斬新なアイディアを、アトラクションのチャンネルで供給することも、業界全体でやるべきだと思います。
原田:『サマーレッスン』は、まだまだ展開中です初めてのVRとしては、絶対感じるものがあります。僕は他社から売れるゲームが出てくると、焦燥感を得たり、嫉妬すると嫌味の一つも言いたくなるんですが、VRってまだそういうゲームが少ないと思っています。「やられた!ちくしょう!」っていうような盛り上がり方がしたいです(笑)
業界的にはみんなが嫉妬するようなコンテンツが出てきてほしいなって思います。
玉置:元年に乗り遅れて手を出さなかったから、やらないというのは、もったいないです。むしろこれからがチャンスです。基本的な勝ち筋というのが見えてきて、それに対してどうやってカウンターを当てるかを考えられる時期というのは市場として、1番新規参入がしやすいはずで、もっとも盛り上がればいいなと思っています。
ーーありがとうございました。
(編集・聞き手:ドラゴン・リバー)
(取材・文・撮影 : 編集部 和田和也)
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)





