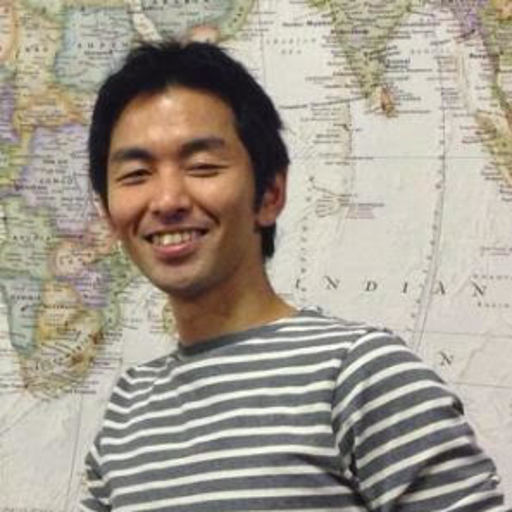【連載】目指すは日本版ネクストA24 。次の才能を育てる「打席づくり」の映画ベンチャーNOTHING NEW 中山淳雄の「推しもオタクもグローバル」第103回
Techベンチャーもあれば、ショートドラマベンチャー、Webtoonベンチャー、マンガAI翻訳ベンチャーなどもある。現在はベンチャー百花繚乱の時代であり、若手がテックの力を使ってエンタメを興そうという機運が高まっている。それは日本のエンタメが海外に向けて展開する素地が整ってきているからだ。だが「映画ベンチャー」というのを聞いたことがあるだろうか?すでに約120年もの歴史がある映画業界は「ベンチャーが生まれにくい」業界の一つだ。好きなものを撮る映画サークルでもたまに自費で映像を作る受託映像制作会社とも違う。あくまで事業計画に基づいて資金調達をして製作-配給-興行という出来上がった映画流通網に楔を打とうとする「映画ベンチャー企業」である。今回は唯一無二ともいえる映画ベンチャーを手掛けるNOTHING NEWに話を聞いた。
【主な内容】
■半世紀ぶりに立ち上がった映画ベンチャー。"映画の鑑賞体験"を再定義し、「体験の総体」を届ける
■飽き性な「なんでもないヤツだった」自分が、イギリス留学で掴んだ「インディペンデント映画との必然性」
■大手映画会社→ノーミーツ→NOTHING NEW:起業への決意
■NOTHING NEW始動、次の「新海誠」は生まれるのか
■半世紀ぶりに立ち上がった映画ベンチャー。"映画の鑑賞体験"を再定義し、「体験の総体」を届ける
――:自己紹介からお願いします
林健太郎(はやし けんたろう)です。映画会社のNOTHING NEWを2022年から創業しております。主に新鋭の作家と共に映画作品の製作を行っており、現在はホラーやアニメーションを中心とした長編作品を準備しています。企画から製作、宣伝配給、海外事業までを自分たちなりのやり方で一気通貫で行える体制を構築し、インディペンデントな作家性を持つ作家やプロデューサーと世界を目指して共闘できるチームを目指してます。
――:いまどき「新しい映画会社ができる」というのは相当珍しいですよね?映画業界は松竹(1895)、日活(現日本テレビグループ、1912)、東宝(1932)大映(現KADOKAWAグループ、1942)、東映(1949)と半世紀以上続く老舗ばかりで構成されている業界です。
相当リスクのあるビジネスでもあるので、今の時代に新しく立ち上げる難度は低くないと感じています。大手の映画会社は不動産の軸など安定した収益源とセットで行っているパターンが多いですが、新規でとなるとそうもいきません。億単位かけて作った映画を一発勝負で展開して、客入りが悪ければ興行(映画館)も数週間で終わるかもしれない。かつ、成功するか否かが分かるまで時間もかかる。そんなビジネスが軸となるので、再現性が求められる「ベンチャー」との相性は悪い、と捉える人も多いと思います。
――:これまでどのくらいの映画作品を作ってきたんですか?
世の中に発表されている作品だと、4名の新鋭作家と共に製作したホラー短編映画集「NN4444」を昨年オンラインで発表し、今年劇場公開を行いました。短編映画から発表した理由は3つあります。1つは、長編映画を共に挑戦する監督と出会う為です。自分たちのような小規模チームがオリジナルの長編映画を製作することは、失敗したら解散を意味するコスト的にも期間的にも大きなリスクのある挑戦です。その挑戦を行う上では、お互いの相性や監督の持つ作家性を深く知る必要があり、限られた時間でそれを実現するには短編映画製作はフィットすると感じました。2つ目は、長編へ挑む前にNOTHING NEWとして自己紹介にもなる作品を作りたかったからです。初めての作品製作の為荒削りで拙い部分もありますが、そこも含めて作り方や届け方、スタンスなど現在地を一度発表することで、この先一緒の船に乗って挑戦をして頂ける作家やプロデューサーと出会うきっかけになればなと。また中長期的に海外市場へも挑戦したいと考えている中で、まずは短編を持って映画祭やマーケットなどに飛び込んでみたいという思いもありました。
――:クリエイターとの出会い、名刺づくり、海外挑戦というのが短編映画から始めた理由ですね。もう成果はあがったのでしょうか?
はじめはオンラインで限定試写的に発表。並行して1作品ずつ映画祭へ出品し、その後4作品まとめての劇場公開を行いました。かなり実験的な方法で展開しましたが、ありがたいことに10以上の国際映画祭へ選出され下北沢K2での先行劇場上映出は2週間連続満席、その後9月まで上映が続くなど、想像以上の結果となりました。
一番印象的だったのは、劇場で短編映画が視聴される文化がない中で事前に盛り上げられないかと行った、オンラインでの先行上映(販売)でした。劇場公開の前にオンラインで展開することは、通常の展開と真逆。ただ結果的にオンライン展開の際に興味を持った方が劇場公開のタイミングで多数訪れることになり、いいプロモーションにもなりました。
――:なるほど、それが「深夜しか見れない映画自動販売機」なんですね。
届け方の1つの実験として行いました。映画の鑑賞体験が一番楽しめる場所は、間違いなく映画館です。一方で、映画館で短編映画をみる文化がまだない中で、その入り口として、間口の広いオンラインでの体験を置くことには可能性を感じています。今回は、"深夜しか見られない映画自販機"をコンセプトに、毎日深夜0時-4時の間だけ短編映画をオンライン上で先行販売しました。Netflixなど配信が普及し、ながら見することが一般的となった中、寝る前に1本集中して映画を見る体験を思い出してほしい、という想いを込め、一度再生すると終了まで一時停止が出来ない設計など"不便さ"を軸にしました。
NOTHING NEWでは映画の鑑賞体験を、映画館へ行く前から鑑賞後までの"体験の総体"と捉えており、これからも鑑賞体験の追求を行っていきたいです。
――:「ショートドラマ」の流れに関してはどう考えていますか?
YouTubeからTikTokへと、スマートフォンで映像を楽しむ際のプラットフォームが短尺に移り行く中で、そういったコンテンツが好まれ始めるのは必然的だと思います。AI技術の発展も合わさり本数も爆発的に増えていき、参戦するベンチャーや映像会社も増え、市場としては急拡大するでしょう。映画業界の人々は映画鑑賞とショードラ視聴は「体験として別物だから影響もない」と捉えている人が多いですが、そんなことはないと私は考えています。作り手としては、作家との新たな出会いの場としてショートドラマにいつか挑む時もあるかもしれません。
一方で、ショートドラマが生み出す映像領域の効率化と瞬間消費の流れが行き着く果ては、どんな世界になるんだろう、とふと思う時もあります。何年後になるかは分かりませんが、全てが効率的に接種でき解決できる世界観になった時は、逆に非効率や不合理な日常に回帰していくのではないか、と妄想しています。全て必要なものは揃っているので、あとは農業をしたり、編み物をしたり、走ったり、わざわざ2時間かけて2000円払ってスマホの電源を落として2時間の映像を見たり。劇場で鑑賞するという"不便さ"自体が価値になっていく時代が訪れるかもしれません。そういった意味でも、前述した"総体としての鑑賞体験"を突き詰めることが映画業界を盛り上げていく上では大事になってくると考えています。

――:ベンチャーなのにこんなになんでもやっちゃっていいものなんですか?
既存の業界慣習などに囚われず、一気通貫で全領域に挑戦することがベンチャーの立場で挑戦するものの役割だと思っています。映画業界は長い歴史がありますが、参入障壁や業態の関係から新しい作り方や届け方に挑戦しづらい部分があります。そこに対して、小さなチームだからこそ自由なアプローチで出来ることはたくさんあると感じています。
――:あまりこういう取り組みで起業されるのを聞いたことないんですが、類似の会社ってあるんですか?
日本国内ではまだ出てきていません。海外だと例えばアメリカで2012年に設立されたA24という会社があります。現在12年目でバリュエーション35億ドル(約5500億円)のメガベンチャーです。『Everything Everywhere All at Once』(2022、興収1.4億ドル)を製作した映画会社です。他の製作または配給作品だとアカデミー賞に選出された『Room』(2015、36百万ドル)、『Ex Machina』(2015、37百万ドル)、『ムーンライト』(2016、興収65百万ドル)や、ホラーファンの間で一世風靡をした『Hereditary』(2018、88百万ドル)や『Midsommar』(2019、48百万ドル)などを手掛けています。
――:ヒットメーカーですね、、、!A24は他の映画会社とは何が違うんですか?
いくつか特徴がありますが、自分が特に突出しているなと感じるのはSNS時代をハックしたマーケティング力です。SNSの登場により全業種がマーケティングを見直していく中で、映画業界はなかなかこれまで行ってきたスタイルから脱却出来ずにいました。その中でいち早くSNS時代であることを最大限に活かした宣伝施策や作品企画に特化し、世間の話題を掻っ攫ったのがA24でした。また、企画/作家を選定する目利き力も唯一無二です。
『The Backrooms』という今製作しているホラー映画作品は、若干17歳のYouTubeクリエイターの原案/監督作品(Kane Parsons、17歳のアメリカショートフィルムディレクター、VFXアーティスト、スクリーンライター、アニメーター、YouTuber)。もう一大企業になったにも関わらず、常に新しい才能を探し求め、尖ったマーケティングを続けるA24は、一つの指針です。
――:とんでもない事例ですね。ぜひ林さんがなぜこんな「ドン・キホーテ」のようなチャレンジングな起業をされているのか色々お聞きしていきたいです。

■飽き性な「なんでもないヤツだった」自分が、イギリス留学で掴んだ「インディペンデント映画との必然性」
――:幼少時代はどう過ごされていたんですか?
小・中学校くらいは飽き性でいろいろなことに手を出していたような子供で、特に何か一つに特化していた記憶はないんです。
高校も一回は体育会系でもやってみようかと思ったんですが、もうその年齢でサッカーも野球もうまいやつはうまいじゃないですか。それでゼロイチで出来そうなものでボクシング部に入ったんですが・・・案の定同期がサッカー部、野球部ばかりで。なぜか1年は続けてたんですが、結局辞めて帰宅部になっちゃうような高校生でした。
――:帰宅部だった林さんがどうやって映画に出会うのでしょうか?
それまではたまにTSUTAYAで映画をレンタルするくらいしか映画に触れる機会はなかったのですが、社会科の先生に勧められて、ドキュメンタリー監督のフレデリック・ワイズマン特集上映を見に人生初のミニシアターへ行ったことが転機となりました。それとほぼ同時にクラスメートが映画の自主制作をしていて、その2つがきっかけでインディペンデント映画にハマり、渋谷ユーロスペースや早稲田松竹などミニシアターへ通うようになりました。
――:その友人の方の映画はどんなものですか?
短編映画で「溝埋め」というタイトルです。もう恐らくどこでも見られない学生映画ですが、生まれ変わりをモチーフにしたユニークな作品でした。当時、インディペンデントな作品を知らない自分にとって、シネコンで流れる商業映画以外にこんな面白い作品がある、と知れたことは、映画の面白さはキャリアや予算とは必ずしも比例せず、新しい才能の作品には唯一無二の価値がある、という今の考え方に繋がっています。
――:自分でも撮っていたんですか?
大学時代に短編映画を数本撮ったりはしていました。その時が映画人生のなかで一番楽しかった時間ですが、これを仕事にして生涯挑戦していく才能は自分にはないな、とも思いました。一方で、作品の企画を考えることや、届け方を考えることは好きだったので、徐々にプロデューサーを目指し始めます。
――:新卒で入社される前に海外にも留学していましたよね。
大学4年のときに1年間、ロンドンの大学に留学していました。映画に限らず様々な文化に触れようと劇場やギャラリーに通いましたが、特に「ビリーエリオット」を鑑賞した体験は今も心に刻まれています。「ビリーエリオット」は訛りの強い英語で自分の知らないミュージカルキャストの出演によって演じられる為、当時の自分には半分の内容も理解できず、キャスト目当てで見る楽しみ方も出来ませんでした。ただ、それでもとにかくその熱量に圧倒されて。エンターテイメントの持つエネルギーは言語も国境も簡単に乗り越えるのだと実感しました。滞在中にバイトで貯めたお金を突っ込み4回通いました(笑)。
ロンドンのミニシアターにも通い詰めていたんですが、ある映画館では毎月ジブリや黒澤明作品、小津安二郎作品など日本の名作が上映されており、毎回満席で。日本映画の力強さを痛感しました。その時、クラシックではない日本映画の魅力も届けたいと思い、当時住んでいた寮の近くであるBrick Laneのギャラリーで小さな映画祭を実施しました。
――:林さんはイベンターなんですか?よく異国の地でそうやってイベント主催できましたね?
いやむしろこの時までは一切何かを主催するなどの経験もなく、留学に行く前までは発想もありませんでした。流され流され、いつの間にかです。そんな自分でも映画祭をやりたいと自然に思えたのは、ロンドンの持つ文化や挑戦に対して寛容な空気感だったと思います。
留学先のきっかけは、大学の授業の一環で「何でもいいから自分で一から企画をする」という授業の演習課題でした。それでせっかくならば、日本のインディペンデント映画を現地の若者たちに見てもらうにはどうすればいいか検証したい、と思い、現地のアートギャラリーを借りて、映画の権利を現地でもっている方に話に行き、ひたすら店やライブハウスにチラシを配ったり、「澪」に協賛をお願いしたり、と手探りで進めていきました。ロンドンの人たちは皆意外にも好意的に話を聞いてくれたので、未経験でもなんとか実施に至れました。
振り返ると、それが映画業界を目指すきっかけという意味では分岐点だったとは思います。結果的にFacebookの告知がきっかけで全回満席で無事終えることができたのですが、その際に現地の人から「日本作品はメジャーもインディペンデントも両方おもしろい」という声を直接聞けたことが衝撃で。"面白い"は規模の大小も国境も関係ないのだなと。今自信を持ってオリジナル作品に挑み続ける原動力になっています。
――:「澪」はちょうど、先週僕も参加したロンドンの日系アニメイベントHyper Japan(HJ)でも大盛況でした。
はい!覚えてます。Hyper Japanでもビラ配りました笑。その時に出会ったことがきっかけで、物品協賛いただいた記憶があります。

▲クレルモン=フェラン国際短編映画祭参加時の写真
■大手映画会社→ノーミーツ→NOTHING NEW:起業への決意
――:帰国後、2017年に大手映画会社に新卒入社されましたキャリアとしてはどういう部署を経験されたんですか?
最初の2年は映画編成・企画の部署にいて、いわゆる映画の川上の仕事を勉強させていただきました。3年目の2019は日比谷シアタークリエというミュージカルの劇場で劇場運営の仕事です。チケットのもぎりなどもやりました。
――:結構映画⇔演劇には敷居が高いと聞きます。相当珍しい異動だったんじゃないですか?しかもコロナ禍での演劇業界の経験も含めて。
ジョブローテションによる異動だったのですが、在籍していた映画会社の中でも相当珍しかったと思います。はじめは「なんで演劇?!」と困惑していたのですが、劇場勤務を通して演劇への想いは募っていき、制作や興行の現場に立てたことは、今にもつながるとてもいい経験になりました。またそのタイミングでコロナ禍となった際に、どうにかできないかと「ノーミーツ」を立ち上げるきっかけにつながっています。
――:本連載でも主宰の1人であった広屋さんに以前インタビューさせていただきました。「会わずにつくる」劇団として2020年に僕もYouTubeでたくさん拝見しました。でも緊急事態宣言の2020年4月7日の手前の4/5時点で立ち上げを決めていたというスピードに驚愕しました。
本業の劇場がすべて止まってしまって、実は並行で自主映画のプロジェクトなどもやっていたのですがそれらも無くなって、完全に自宅待機になってしまいました。当時は「このままずっと劇場は閉じられてしまうかもしれない」という恐怖感のなかで、ネット自体を作品発表の場にすれば、自宅から創作や芝居を発信する機会になるかと思ったんです。
――:ノーミーツの勢いはすごかったですよね。文化庁芸術祭やAMDAward、ACC Tokyo Creative Awardsなど広告賞も総ナメでしたし、なにより“演劇界の芥川賞"といわれる岸田國士戯曲賞にノミネートされたときは、嫉妬も含めて反応すごかったんじゃないでしょうか?
そうですね。特にうれしかったのは文化庁メディア芸術祭での選出でした。ノーミーツの劇団自体を作品として選出してもらったのですが、自分はノーミーツを創作団体というよりかはコロナ禍に試行錯誤をしながら可能性を追求した一つの作品だと思っていたので、その挑戦自体を認めていただいた、という点で達成感がありました 。
<劇団ノーミーツ時代の企画>
20作以上の「短編Zoom演劇作品」では累計再生数3,000万回」突破
1.第1回長編公演「門外不出モラトリアム」(2020年5月;2,500円×約5,000人が観劇):「もしもこの生活が、あと4年続いたら。」をキャッチコピーに、Zoom上で展開される演劇作品。入学から卒業まで一度も会わずに過ごした5人の大学生を描いた。
2. 第2回長編公演「むこうのくに」(2020年7月:2,800円×約7,000人が観劇):「世界はひとつになった。はずだった。」をキャッチコピーに、AIの友達を探す主人公・マナブの成長物語を架空のSNS「Helvetica」を舞台に描いた。劇伴をパソコン音楽クラブ、主題歌をYOASOBIが担当。
3. 第3回長編公演「それでも笑えれば」(2020年12月:3,000円×4.000人):人生の"選択"をテーマにした2020年を締めくくる物語をテーマに、女性お笑いコンビの2020年の出来事を描く。観客の選択が物語の行末を左右する"観客選択式演劇"という形式で、オンライン劇場「ZA」のこけら落とし公演として上演。劇伴をodol、主題歌を羊文学が担当。
4. コラボ公演「VIVA LA VALENTINE」(2021年2月:3,800円×5,000人):サンリオピューロランドでの共催企画として上演。閉館後のピューロランドを舞台に、ワンカットの生配信演劇を実現。ノーミーツとして初めて、「会って物語を届ける」形式への挑戦。
5. コラボ公演「HKT48、劇団はじめます。」(2021年3月:2,800円+α×10,000人):HKT48との共催企画として上演。通称 #劇はじ は、企画・プロデュース・脚本・演出・衣装・美術・音響・映像・配信・広報・出演を全てメンバー自身が担い、オンライン演劇をつくる前代未聞のプロジェクト。その様子をドキュメンタリーとしての過程を発信し、2チームに分かれての上演を実現。
6. コラボ公演「あの夜を覚えている」(2022年3月:4,200円+α×約24,000人):ニッポン放送との共催企画として上演。オールナイトニッポン55周年記念公演として、ニッポン放送の実際の館内から届ける生配信舞台演劇ドラマ作品として実施。W主演に千葉雄大、髙橋ひかる。総合演出にテレビディレクター佐久間宣行、主題歌をYOASOBI×Creepy Nutsの描き下ろしコラボ楽曲が実現。
<劇団ノーミーツ時代の受賞>
第24回文化庁メディア芸術祭エンターテイメント部門優秀賞
第26回AMD Awards '20 優秀賞
60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSクリエイティブイノベーション部門 ACCゴールド
――:すでに映画会社の中でもキャリアを築かれはじめ、ノーミーツも順調にいっていました。そうした中で、あえてどちらも捨てて「自分でNOTHING NEWを起業」という方向にいったのはどういう理由だったのでしょうか?
ノーミーツで初めて、それまで前例のないことに挑戦できたことがとても大きかったです。ノーミーツは最初の頃、特に業界の方々からこれは演劇ではない、上手くいくはずがない、と言われ続けたのですが(有料公演の実施は他のメンバーにも難しいと言われてました(笑))、初めて有料で行った生配信公演『門外不出モラトリアム』を上演した際に、一つの作品として一定評価されたくさんの方々に楽しんで頂くことができました。振り返るとそのこと自体は無鉄砲なラッキーパンチだったと思うのですが、「必ずしもそれまでの常識や固定観念が正しいとは限らず、無知な人間だからこそできる大きな挑戦もあるのだ」と知れたのがその時でした。
コロナが少しずつ収まり、再び映画業界へ目を向き始めたのですが、その時に、高校時代の時からの夢である、新しい世代の才能との世界を目指した映画づくりに改めて挑戦したいと思いました。しかし、それが実現しづらい環境は10年前から変わっていなかった。映画業界には才能発掘の動線の不在など様々な構造的課題があり、今いる大手の映画会社からではスピード感を持ってチャレンジをするのは難しい。そう感じたことから、2022年4月に新しい才能とのものづくりに特化する映画会社NOTHING NEWを始めました。
■NOTHING NEW始動、次の「新海誠」は生まれるのか
――:2020年に大手映画会社にいながら劇団ノーミーツを立ち上げ、その上で2022年には映画会社を作ろう!という林さんのアヴァンギャルドさに驚かされました。
自分の中では最初「起業」の選択肢は持っておらず(というか知らず)、実現したい構想だけがある、事業計画も何もないところから、2022年4月に前職を飛び出て登記をしました。その後、周囲の友人などに起業やスタートアップなどのことを教えてもらいながら、ご縁あり22年末に資金調達を行い、2023年から本格的に始動をしました。
ちなみになのですが、そもそも「スタートアップとは」という仕組みを全く知らないところからスタートした中で、基礎を教えていただきスタートアップへの挑戦にも導いてもらったのは、中山さんも社外取締役をされているPlottの奥野翔太さんです。
――:なんと、そんなに近い関係性だったんですね!?
はい、初めて出会った時は自分がまだ社会人2年目くらいの頃。社外で企画や映像制作の活動をしていたのですが、ある日、当時まだ会社も黎明期であっただろう奥野さんからYouTubeチャンネルの脚本をお願いできないか、とDMを頂きました(当時は奥野さんが起業家、であることすらも知りませんでした(笑))。
自分はキャパシティ的に難しそうだったので、先ほどお話しした自分が映画に進むきっかけとなった作品「溝埋め」を監督した比企さんを紹介しました。彼は現在もPlottさんで脚本を書いており、なんだか不思議なご縁を感じています(笑)。。
――:映画や演劇を作っていた林さんからするとPL・BSつくって投資家に説明してといった作業はストレスが多いのではないでしょうか?
起業して少し経った頃にCOOの下條が加入して初めて「キャッシュフロー」がマズいということを知りました笑。この会社を「会社」にしてくれたのも下條のお陰です。ファイナンスやスタートアップ領域と距離が遠いことも、映画業界から新興企業が生まれづらい一因かもしれません。
――:今何人くらいが関わっているのでしょうか?
事業の方はフルコミットで4人目が入社したところで、現在アニメ制作も自社で行っているので、そのチームが10人ほどいます。
――:でも「インディー映画振興」というところで実は私も疑問があって。日本はインドや中国に並ぶような「映画生産大国」で邦画だけで毎年500~600本も上映されていて、本数だけでいえばハリウッドを越えています。そうした中でそれでもインディー映画振興というのは必要なものなのでしょうか?
映画の本数自体は十分にありますし、アニメや一部実写作品の盛り上がりは国境を越え始めている。業界自体には大きなポテンシャルを持っていると思います。海外のプレイヤーと会話をしていても、日本の作品や企画を欲している人たちは少なくありません。
ただ、映画をつくる人材の視点からでみると、かなり危機的な状況です。若手にはチャンスが少なく、キャリアステップも不明瞭で、大手映画会社がヒットする作品にのみ本数を絞る傾向は変わらない。新しい才能を発掘する「打席」は現在の国内映画市場では少なくなる一方です。作家はみな過酷な環境のなかで、どうにか自腹を切って自主制作映画をつくるのですが、作ったとしてもどうしたら世界へ挑んでいくかの動線は不明瞭であり、もしそこで頑張ってよい実績を残したとしても、そこからメジャー作品に続く導線も多くありません。
例えば、漫画業界を例に挙げると、集英社の週刊少年ジャンプはあれだけ大きくなっても常に「新人発掘」を行い続けています。さらにはジャンプ+もあり、あらゆる切り口で新しい才能へ投資をしフックアップを広く行っています。これは、ビジネス的成功のためにも文化を発展させるためにも、新しい才能に投資を行わなければならない、ということが当たり前として認識されているからです。映画業界には、その当たり前の空気感が、まだ残念ながら存在していないのです。
――:なるほど、そういう点も含めて「打席づくり」で経産省のほうにも関わっているんですか?
2024年7月から「創風」という経産省のプロジェクトの「映像・映画」部門に運営として参画させてもらっています。「ゲーム」「映像・映画」の2部門で審査に選ばれたクリエイターが1年かけて制作から展開までもっていくことをメンターが伴走しながら支援するプロジェクトです。個人で応募でき、支援者が経産省なので著作権も全部クリエイターに残るところも特徴。1個人・1チーム支援上限500万円。現在は選出された第一期の10名と共に作品づくりを行っております。みなさん高い熱量と個性を持っており、同業者として非常に刺激を受けております。
クリエイター支援を直接行うことは経産省としては珍しく、官民連携で新鋭作家をサポートする流れを生み出すための、小さいですが大事な一歩目になると感じています。5年10年と続けていきたいです。
――:NOTHING NEWでの活動や創風を通じて、林さんはどんなことを実現したいんですか?
まずは「新しい才能がオリジナル作品に挑戦できる打席を増やすこと」を考えています。そのための第一歩は、まずは自分たち自身が作り手として実際に新しい才能と作品をつくり、国内外の作品評価と興行両方で成功する事例をつくること。それに尽きると思います。
やり方も、大変ですが出来るだけ内製にして、これまでの固定観念に囚われない形で作り方から届け方まで一つずつ再定義していく。それがまずは1作品で実現できれば、業界に一石を投じることができるかもしれない。それが2作品になれば、才能への投資に業界全体が興味を持ち始め、作品数が続いていけば、新しいムーブメントに繋がる。そして、いずれ新しい才能の作った作品が大ヒットし、その資源で次の世代へバトンを繋いでいく、一つの循環になっていく。それが当たり前になっていく。そんな文化を目指したいです。
――:才能の発掘でいうと、『雲のむこう、約束の場所』(2004)、『秒速5センチメートル』(2007)、『星を追う子供』(2011)で新海誠さんの作品作りを支援しつづけてきたコミックス・ウェーブ・フィルム(CWF)がまさにやってきたことですよね。『言の葉の庭』(2013)から東宝さんが入って、『君の名は。』(2016)につながっていきます。
そうですね。CWF川口典孝さんが新海誠さんを見出して、才能が世間に見出されるまで粘り続けた。そして大ヒットまで伴走し続ける。ある種狂気的な熱量にも見えますし、本当に信じているからこそ本人の中だとシンプルに粛々と行っていたことなのかもしれません。自分の選択した道を信じることの大切さは、勝手に川口さんの歩んだ歴史から学ばせて頂き、今でも心の糧になっています。
――:林さんは、どのような才能のあるクリエイターと作品づくりを行いたいですか?
世界で誰も持っていないようなごく私的な変態性を持ちながら、世界中の人に届けたいというある種の貪欲さもある、その矛盾とも言える剥離の大きい人が、自分が生涯作っていきたい作家です。そういう作家と出会った時に、一番思い切ったチャレンジができるために、NOTHING NEWを頑張っています。
――:そういう才能に何を掛け合わせたらスゴイ作品になるのか、というところは運の要素も強いですよね。
完全に科学できてヒットに再現性を持たせられるのか、というと、もちろん難しいです。ただ、研究出来ることは少なくないと思います。例えば『Backrooms』(2019)や『Talk to me』もYouTubeというプラットフォームから生まれた企画です。そうした流通の刷新は、新しいものや、才能が生まれてくるきっかけになるはず。
AIや最新技術の発展により、マンガ・ゲーム・映画などの領域が融解していく予兆も感じています。自分たちが製作した映画「NN4444」の映画ポスターもAIアーティストのyuma kishiさんが作品をAIと一緒に解釈して作成したビジュアルです。自分はAIに対しては、効率化や利便性よりも、むしろ新しい映像表現の発明や、新しいセンスの映像作家の出現に期待しています。NOTHING NEWとしては、そうした技術やビジネスモデルの刷新のなかで大手ではなかなか踏み込めないトライアルも続けつつ、まずは自分たちの名刺となる作品を発表していきます。作品が公開される際は、ぜひご鑑賞いただけると幸いです。

会社情報
- 会社名
- Re entertainment
- 設立
- 2021年7月
- 代表者
- 中山淳雄
- 直近業績
- エンタメ社会学者の中山淳雄氏が海外&事業家&研究者として追求してきた経験をもとに“エンターテイメントの再現性追求”を支援するコンサルティング事業を展開している。
- 上場区分
- 未上場