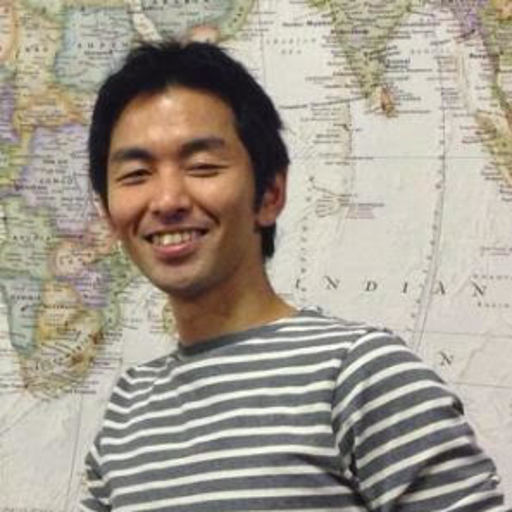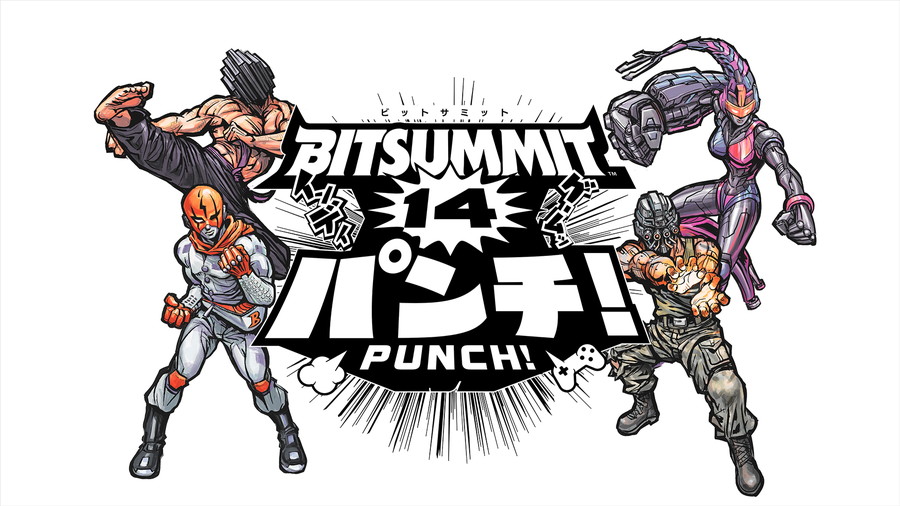世界エンタメ特集「中国・長沙編」―第二回:お菓子屋が1兆円。中国Retailer Excellenceに日本が学ぶべき理由
■“お菓子は忙しい” 零食很忙(Snack is busy)、お菓子小売が8年間で1兆円企業に
零食很忙Ling xi hen mangは、日本でいうと「おかしのまちおか」のような菓子専門小売業だが、驚くべきは2017年設立以来8年で年商8000億円、全1.6万店舗の規模にまでのぼりつめた成長スピードだろう(おかしのまちおかは埼玉県の老舗(株)みのやが1997年に新規展開した業態で、年商200億円、全国160店舗)。
コロナ後に成長は加速しており、2023年には江西省宜春市の趙一鳴零食(こちらも2019年設立)と合併し、新たに鳴鳴很忙集団(MMHM Group)というグループ名に改称。2025年の今年中に2万店舗を突破する見込みで、日本のセブン・イレブンを超える店舗数となる。1日500万人が入り、2024年は1年間でのべ16億人のユーザーが利用した。
中国人はそんなにお菓子が好きなのか!?と思いたくもなるが、その実、食品の小売業における革新的なビジネスモデルによる成功事例だった。商品はとにかく、安い。水のペットボトルが相場2RMBのところ1.2RMB、コーラ1缶2.5RMBのところが1.8RMB。都会の店舗においても3-4割ほど安く、地方にいっても競争価格を維持できるのはディストリビューターをいれずにメーカーと直取引を行い、特に中国では効果の大きい「現金仕入れ」だ。現金化するまでの30-40日間といった支払いサイトのリスクをサプライヤーは金額をのせてマージンとしてくる、もしくは品質を下げてくる。在庫コストも資本コストも無駄、より安い値段で直接購入するためにこの「現金仕入れ」というのは実は非常に有効な取り組みだ。
200平米ほどの1店舗で半径1kmの1万人を商圏として商売をしており(コンビニで半径500m)、週2回ほどくるお客の客単価は800円ほど。利益率の安い商品を個包装でとにかく単価低く多品種で商売しており、1店舗内にある商品は2000SKU。そのうち600SKUがばら売りというほど、数十円単位の小さいお菓子が大量に陳列されている。広い店舗でも基本的にはカウンターにいる数名のスタッフだけでまわせている。これほど多品種で細かい商品のレジ打ちは、バーコードすらなくカメラでAI判定され、短時間で計算可能な仕組みが有効に作用している。
流通や小売りのリベートがない、ということが業界的には革新的であった。そこに来店頻度と棚効率のよいものだけを選ぶ(月8回という在庫回転率は驚異的だ。日本のコンビニですら月2-3回)。長沙都心のこの1店舗で日販1.3万元(約30万円)。とにかく出てくるKPI、出てくるKPIが衝撃的なのだ。ゼロイチをつくっているエンタメ業界からすれば見落とされがちだが、こうした「末端で顧客接点をもつプロセスをいかに効率化し、大量の人手と場所を使いながらハイクオリティなサービスでユーザーを魅了するか」という点は、アニメ・ゲーム・マンガといった産業においても必要な知見だろう。



創業者は1987年生まれのミレニアム世代。不動産マンション販売をしていたついでに副業で小さなお菓子店を経営していたが、この低粗利な商売は回転率さえあげればそれなりの規模になるのではと一念発起で本業としてスタートさせた。湖南電視台(MangoTV)でもどんどん取り上げられ、経営の中身は本当にスケルトンで誰に知られてもいいようになっている。それ自体がブランディングなのだ。
「我々はリテールではない」という発言が衝撃だった。リテールビジネスの要諦は品質価値、情緒価値、効率の3つであり、この店は効率と品質を徹底的に鍛え上げた上に、一番大事な情緒価値という余剰部分に一番気を使った設計をしている。必需品ではないものを売っているため、いわゆる「目的買い」でお客さんは店舗にはこない。だから行けば何か発見があるというワクワクした体験こそが一番の来店動機なのだ。
どこかで聞いたことがある話ではないだろうか?そう、実はこのお菓子店が目標にしているのは日本の「ドン・キホーテ」だ。その商品設計から陳列の方法に強くインスパイアを受けた、という。現在も年に3-4回は日本に出張し、各小売店の優れた仕組みを学んでいる、という。同社オーナーが目標として掲げた「ドン・キホーテ」を追求した結果、まさに体験型店舗として「零食很大(Snack is big)」という600平米の大型お菓子の店舗をつくってしまった。人間の顔サイズのマシュマロや身長の高さまであるオレオといった「とにかく巨大なお菓子に囲まれる」体験ができるこの店舗は観光地化しているが、驚くのはそれは単なるモニュメントではなく、すべてが購入できるリアルのお菓子なのだ。180社のお菓子メーカーと提携し、この店舗のためだけにフルカスタマイズで100倍サイズのお菓子を作ってもらっている。


この巨大お菓子の体験店舗は現在3店舗展開、非常にコストがかさむ取り組みだし実際にこんな巨大なお菓子を買う人はいないのでは!?と思ったが初日は2000万円の売上。2024年の開店後半年でも14億円もの売上開店後の写真は全国で話題となり40億回再生のトラフィックを生む結果となった。ブランディングにも有効で採算があうということで2店舗目、3店舗目と出店するに至った。月1回はメーカーとダイレクトのブランディング施策をしており、今回訪問した際に玄関口でコラボをしていたのはサンリオであった。今後はお菓子以外にぬいぐるみ、フィギュア、カードゲームといった商品展開も考えている、という。
零食很大は極端なモデルだが、巨大化したリテーラーがむしろ川上のメーカーに圧をかけて、ユーザー需要にあわせた製品をつくるよう促すのも、重要な役割だ。最終的には6-7万店舗までの拡大を目指している。現在6000万人いる湖南省で2500店舗を構えるが、実はパクリ店舗も2500店あるという。本家と同じだけ、パクリ店舗が発生してしまうということも中国ビジネスの難しさを物語る。

中国あるあるで「隣にパクり店」が堂々と構えられていた。零食很忙ではなく「小猫很忙(子猫は忙しい)」とここまで真似てよいかのかと思えるレベルだが、オペレーションは真似できなかったようだ。非常に閑散としており、すでに閉店が決まった在庫セールをしていた
海外への展開も検討の余地はあるが、ベトナムなど近隣国には中国ほどに川上の製造が育っていない。ベトナム全土でお菓子をかき集めても2000SKU、しかもほとんどが外資系のナショナルブランド、ということでこれだけのバラエティの商品をそろえられるという点もそれなりに成熟した消費大国中国ならではというメーカーとの共同作業の結果なのだ。
今後小売のリアル店舗はどうなるのか?オンライン業態にずっと劣勢になっていくのでは?という質問に対しては「1ケースを売るのにはオンラインのほうが便利だが、1袋を売るのはリテーラーが優位なのだ。単価の小さく、目の前にある情緒的価値をもった商品を売るという点でリアルな顧客接点のある店舗にはオンラインは勝てない」とのこと。拼多多(Pinduoduo)のような巨大なオンラインディスカウンターに対しても、ポジションをとれている。
直営店とフランチャイズ店があるが、「弊社はフランチャイズオーナー管理システムでは中国一の自信がある」という。70~80万元(1400~1600万円)かけてフランチャイズ店舗となったうえで、商品サプライなどは本社が管轄し、商売自体はフランチャイズオーナーが主体となるのは日本のコンビニと同じである。店舗数2万もこえてくると、フランチャイズオーナーの質もバラバラ、投資目的で店舗クオリティが低いところも増えてくる。そうしたフランチャイズオーナーの教育センターにも投資し、全体の品質コントロールも行っている。
■コンビニチェーン新佳宜xin Jia yi(New Joy)、中国ローカル型垂直統合
長沙版コンビニの新佳宜xin Jia yiもまたリテール・エクセレンスが光る企業である。2007年に設立し、10年以上かけて日本型コンビニをローカライズして1000店舗まで広がった。だがコロナで消費の切り替わりがあり、そのままではもう拡大しないと感じ、事業転換を図った。それまでは常温商品ばかり扱っていたコンビニだが、冷たい牛乳や賞味期限28日間で廃棄する冷えたビール、ホットドックといった温度管理ができるコールドチェーンを築いたのだ(日本では当たり前だが温度管理ができる物流網をゼロから作るということ自体が2020年前後の中国でも大工事だった)。

驚くべきはそのスピードだろう。2019年までに増やしていた旧型の1000店舗は、2020年に事業を切り替えた時に全部つぶした。現在そこから5年かけて増やしてきた1300店舗はすべて新しく作ったものだという。なんというダイナミズムだろう。実はコロナ前は同様の業態で200店舗ほど作っていたがあまり儲かっていなかったという。明らかにコロナ後に顧客の消費特性が変わり、近隣のコンビニに温度管理商品を求めるようになったのだ、という。それまで常温牛乳を買っていた客層が、ECで同様のものを入手できるようになったために、むしろコンビニで冷えた牛乳を積極的に買うようになった。「牛乳は冷たいものだ」という観念自体もこの新佳宜によってつくられたといってよい。
商品種類は1000SKUで決して多いわけではない(日本ではセブンイレブンが5000SKU、他のコンビニ平均が3300)。だが温かいもの、冷たいものなど「温度管理ができた商品」がクセになる。1店舗あたりの日販は8千元(16万円)、中国においては一番高いクラスの日照になる。80%フランチャイズ:20%直営店でフランチャイジーは約1000万円ほどかけてチェーンにはいるが、どの店舗も2年ほどで十分にペイできるという。強みは温度管理できた「PB商品」である。当然利益率も高い。売上ベースでは5%だが、利益ベースでは20%がPB商品である。1SKUあたりで20億円ほど売ることを目標に、自社で商品開発をしている。弁当はそんなに売れないという。
客層は「1日に10元(2千円)しか使えない人々」だ。月収6-7万円クラスのワーカーたちが一体なにを食べたいのか。それを考えた商品づくり、デリバリー設計を行っている。
物流も倉庫も全部自前だ。なんなら中食工場まで自前で立ち上げようとしている。まるで神戸物産だ。日本ではBSに重くのしかかる工場部分を中食業者に委託する分離経営モデルをとっている。連結性の高い日本であればそれで機能するものが、ないないづくしの中国ではそれらを垂直統合型にまとめ上げる。ここまでやってこそのコンビニチェーンなのだ。プラスチック容器の工場まで自前で持っている、というのはあまりに非効率に感じたが、それもまた中国における効率の正解なのかもしれない。
競合のコンビニは常温商品が主体で、かつボランタリーストア(本部で仕入れせず、各店舗が発注)モデル、店舗ごとの質もまちまちで新佳宜と競合することはない。日系コンビニも同様だ。ローソンやファミマといった日系コンビニは「1.便利、2.品質、3.価格」という優先順位で、新佳宜はむしろ「1.品質、2.価格、3.便利」という順番で、多少立地が不便でも品質がよいものを安く提供できるほうが優先度が高い。それは地方にいけばいくほどその傾向が強い、とのことだ。
むしろライバルといえるのは前述の零食很忙だ。どこまで増やせるかといえば「零食很忙の3倍」という。お菓子店舗が100店舗あるなら、コンビニは300店舗は増やせる。現状長沙市内に零食很忙が200店舗あるからこそ、新佳宜も900店舗配置している、という状況だ。これから湖南省の地方部にも展開していく。地方にいけばいくほど需要はあっても供給が不足しているから、そのまま差別化できて売上もよりよくなる、という。いまは毎月50店舗のペースで増えており、拡大路線一辺倒だ。
コンビニというすでに常態化したビジネスモデルで、効率の悪い地方で勝つコツはと聞くと「コールドチェーン、デリバリー、夜間消費。これが地方で勝つポイントだ」という。すでに売上の10%はデリバリーだが、地方部に行くとすでに25%というところもあるようだ。オンラインの線が行き届かないエリアでは、リアル店舗からのデリバリーがより有効なラストワンマイルになるのかもしれない。夜間時間が1日の日販の25%を占めるという。これは滞在時間そのものが娯楽になる、特に娯楽のすくない地方部においては特にその機能が有効、という零食很忙の話にも通じている。
コンビニは日本の専売特許ではない。1990~2000年代が日本のコンビニ戦争の黄金期だったが、2010年代はその成長を国境を越えて広げ、いまやセブンは国内2.1万店:海外6万店、ローソンは国内1.6万店:海外0.7万店、ファミマは国内1.5万店:海外0.8万店。各社ともにアジアを中心に海外で店舗数をどんどん増加させている。そうした「日本発グローバルCVSチェーン戦争」のなかで、実はローカルで独自進化したコンビニチェーンもまた活性化している。たとえば筆者も昨年調査したポーランド では市場の時価総額No.1はZabkaというコンビニチェーンで、その売上8000億円超という実績は出店効率を上げ、商品管理/在庫管理を最適化し、アプリ導入で顧客との結びつきを強めたデジタル化の恩恵である。東欧ではDX化こそがコンビニの勝因であった。だが中国においては必ずしもそれが正解ではない。絞ったSKU、チェーンの自前化、リテーラーがPB商品まで開発、容器工場の内製化など日本では考えづらいことまで垂直統合している。

なぜ方向転換したのか。それは「このままではECに勝てない」と思ったからだという。ただECでも買えるものを近隣で便利だからという理由だけで商売をしていてはいつかは覆される。あえてリアルの場所に立ち寄って購入するからには「理由」が必要であり、それはECデリバリーでは実現できない「できたて温かいもの」か「よく冷えたもの」などとにかく温度管理がされているものだ、という確信があった。
創業者の伍敏渲は実は医者出身の起業家である。もともと実験室で研究をしているような医学生だったが、ロジックで何度も試行錯誤しながら丹念に実験しつづけることを強みとしていた。だから立地で差別化、商品で差別化と色々付け替えながら様々なカスタマージャーニーをみていき、最終的には「温度管理商品こそがコンビニの生きる道だ」と気づけた、という。
この先はどうなるのか。現状は1000店舗だが、湖南省だけで3000~4000店舗にはできる自信があるという。競争相手はお菓子屋だったり飲食店だったり、それこそ店頭でフルーツジュースを売るパパママショップだったりする。そうした「出来立てを食べられる」という点においてまだまだ改善の余地があるのだ、という。
■消費発展元年に輝く、長沙。旺盛な起業家組織から日本リテーラーが学ぶべきこと
長沙新消費研究院(日本でいえば生産性本部、日本能率協会のような組織)で「なぜ長沙でこうしたコマースの革新的な事例が次々と生まれるのか」という話を伺った。所長曰く、長沙の発展に寄与した“両親”がいる、という。“父親”は地方政府だ。湖南省は毛沢東の生誕地でもあり、他省では難しい先進的な取り組みなども強い自治権をもって推進することができた商人の街である。起業エコシステムが育ったのはこの生誕地特権が大きかった、とも言われる。
そしてそこで多くの人材を生み出した“母親”とも言えるのが湖南テレビである。日本の状況と大きく違うのは政府とテレビ局が一体となって経済の中心軸を動かし、起業家精神を掻き立て、そこで育った人材が民間に飛び出して様々な起業エコシステムをつくる。他省からも視察の列が絶えず、多くの口にのぼるのは「再現性があるのは湖南モデル」ということである。もちろん中国における最大都市というのは上海や北京、そこに広州・が「超一線都市」といわれる巨大な都市圏である。ところがそれらはもともとあった立地や歴史によって発展したものも多く、23省、691都市からすると模倣するにはあまりにその背中が遠いのだ。そうしたときに中国全土の地方都市が目先で目標としているのが「湖南省」なのだ。
これまで30年が「生産発展」の時期であったとすれば、2025年は中国にとって「消費発展元年」になる。外需・輸出で成長してきた中国はすでに1人あたりGDPでも飛躍的に伸びており日本へのインバウンド需要でも2~3割が中国人、というのが現状だ。1980-90年代の日本人のような旺盛な消費意欲はいまは誰もが知るところだろう。だがこの15年ほどのそうした急速な動きが2024年に一服、いまは「成熟期」に差し掛かっている危機感もある。そうした中で「長沙」はそのGDP以上に重要な位置を占めている。
この地は外国人旅行客も少なく、住宅価格がおさえられた分だけ上海・北京に負けない可処分所得をもつ地方富裕民が集まり、「国内消費のモデルケース」になっている。「赤壁の戦い」などでも有名なこの地は北に巨大な湖、南に山脈を構え、日本でいうと京都のような地形をもつ。夏は非常に蒸し暑く、冬は大変に寒い。こうした気候の変化がさまざまな消費欲を掻き立て、感情表現豊かで「スパイシーな女性が多い」と院長は笑う。
今回は小売リテーラーのエクセレンスに注目した長沙出張であった。上記のほかにも茶葉の風味を生かした「茶顔悦色」というティーチェーンもまた長沙で数千店という単位で展開する成功小売チェーンである。だがチェーンストアばかりではない。オンラインストアでも優れた企業が長沙から生まれている。Amazonで一番売れている靴が長沙製だったり、電機機器でECを使って大きく伸ばしたAnkerはいまや日本人もよく使うブランドになっている。アウトドア珈琲マシン企業、中国ボディーケア製品ブランドなど日本人の知らない、成長ブランドはいくつにもわたっていた。
ただ課題はまだこうした製造からのサプライチェーンは沿岸部のみで固まっているという点だ。工場も物流もオペレーションセンターも沿岸部におかれ、今後内陸部にも移管していくといったフェーズにある。だからこそ新佳宜のように自らコールドチェーンを作り替える必要があったのだろう。
ひとつ前の世代にはサプライドリブン(生産量勝負)だったものが、Z世代以降はデマンドドリブン(需要勝負)になっている。家族単位での消費購買が、個人単位の消費購買になっている点も加味しなければならない。そして機能価値はもはや差別化の道具とはいえず、情緒価値をどう商品ごとに高めていくかが重要なポイントだ。こうした中国における世相分析はそのまま日本にも当てはまる話だ。
改めて今回を振りかえり「起業家の出自」というのは大きく作用するのだなと思う。不動産店舗出身の晏周は、どんどん立地を広げて面をとっていくことを得意としてきた。医者出身の伍敏渲は、コンビニをひとつの人体に見立て、様々な実験を重ねることで何が一番効果的に効いているのかを分析していた。こうした中国リテーラー・エクセレンスはMBAはおろかビジネス本としてもほとんど紹介されることがない。しかしながら、トヨタが「日本にアメリカ車がきたら日本の自動車産業はつぶれる」という壮絶な危機感のもとに「フォードは間違っている」と日本式の生産方式を四苦八苦試した結果がカンバン方式で、1950-60年代にすでに実践で実現していたものだ。それが公開され形式知となったのはほぼ1980年代になってからの話。米国市場で圧倒的な競争優位をもった日本車になんとか追いつこうと学び、それをシックスシグマといった形で米国メソッド化した時にはもう1990年前後になっていた。
アメリカは日本のプロダクション・エクセレンスに気づくのに30年もの時間を無駄にした。それでは中国におけるコマース、リテールの革新的な変化を、日本企業はいつになったら学べるのだろうか。MINISOをみれば『サンリオ』『ちいかわ』『クレヨンしんちゃん』『ちびまる子ちゃん』といった日本IPグッズが並び、彼らはいままさにそれを中国外のアジアや北米へ運んでくれる“革新的なIPリテーラー”の役割を果たす。なぜ日本のリテーラーにこれができないのか。まさか2040年代になってからようやく、ということはあるまい。



会社情報
- 会社名
- Re entertainment
- 設立
- 2021年7月
- 代表者
- 中山淳雄
- 直近業績
- エンタメ社会学者の中山淳雄氏が海外&事業家&研究者として追求してきた経験をもとに“エンターテイメントの再現性追求”を支援するコンサルティング事業を展開している。
- 上場区分
- 未上場