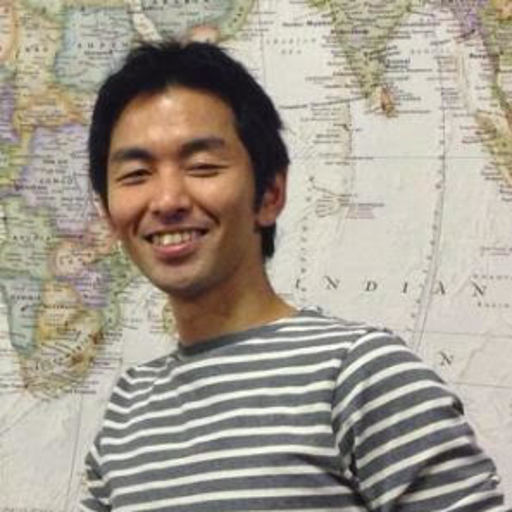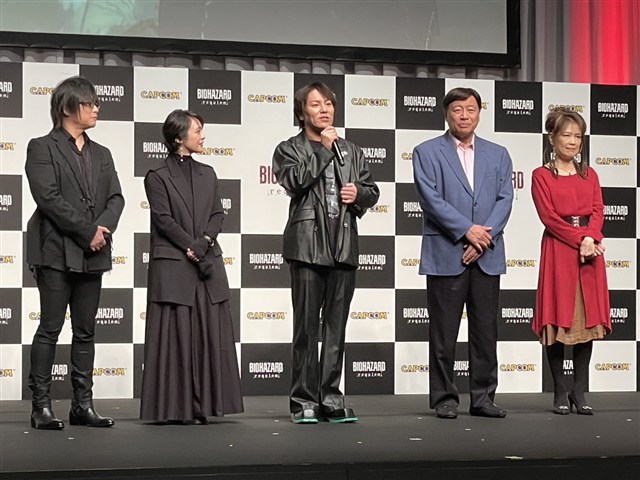ハリウッドで12億ドルをつかみ取った弁護士。SEGA役員&ハリウッド映画プロデューサー中原徹のミラクルキャリア 中山淳雄の「推しもオタクもグローバル」第126回
中原徹氏は弁護士(日本、カリフォルニア州、ニューヨーク州で登録)でありながら、ゲーム会社SEGAの執行役員、そしてParamount『Sonic the Hedgehog』というシリーズ3部作にプロデューサーとして名も連ねている。3作累計10億ドル(約1500億円)の興行収入は「ハリウッドのプロデューサー界」の中でも金字塔である。なにせ歴代300名強しか到達したことのない領域であり、それだけ稼いだプロデューサーは7割米国人、2割英国人で日本人は中原氏ただ一人。なぜ一介の弁護士、ゲーム会社の役員が、このようなレコードを得ることができたのか。そこには日本の映画界が世界に羽ばたくためのヒントに溢れていた。今回は「ハリウッドにプロデューサーとして入り込んだ人物」としての中原氏にインタビューを行った。
■世界映画プロデューサートップ300位にランクインした日本人弁護士
――:自己紹介からお願いします。
中原徹(なかはらとおる)です。SEGAの上席執行役員、映画/TV制作統括プロデューサーを務めております。
――:中原さんといえば「弁護士」であると同時に、「ハリウッド映画プロデューサー」です。こちらのサイトでも、Top Grossing Producerで世界トップ300にランクインされています。日本人で他に入っているのは鈴木敏夫さん(418位)くらいでしょうか。もともと弁護士ですよね!?
そうですね、いまはリーガルの部分はほとんど担当していなくて(笑)。先ほどもポール・W・S・アンダーソン監督(ミラ・ジョヴォヴィッチの夫)とディスカッションをしていました。まさかこんな仕事をSEGAでやることになるとは思っていなかったですね。
世界の映画プロデューサー興行収入ランキング
▲Numbersより中山作成
――:2015年にSEGAグループに入社されてからちょうど10年強が経ちました。現在の業務の割合は、どんな感じなのでしょうか?
今している仕事はクリエイティブ50%、そしてプロジェクト実現のために必要なコミュニケーションや人間関係構築などで25%。残った25%でビジネス=契約書関係に対応しているという感じでしょうか。最後に一番大切なことはお客さんが喜ぶクリエイティブなので、なるべくそこに一番注力するようにしています。
もちろん最初からこんなことができたわけではないです。最初は「弁護士が何言っているんだ」みたいな雰囲気もありました。でも成功した/失敗した映画を何百本もきちんと観て分析して、その映画のポイントを引用もしながら「ここのセリフや設定は、本当に面白いのかな?」と代案をもって脚本会議で議論すると、そこに合理性がある限りはフェアに聞いてくれます。「このキャラクターの動機が不明瞭ですよね?」「このジョークはウケなそうじゃないですか?」など脚本の1行1行を分析して、理由付けや提案をする、という作業を今は一番メインでやっていますね。
――:その仕事内容にビックリです(笑)。日本人でハリウッド映画の制作プロセスで「プロデューサーとして、ビジネス(契約)とクリエイティブどちらもやっています」という人って他にいたりするものでしょうか?
両方やっている人はあまりいないかも知れません。役者側からという意味ではマシ・オカさん※だったり、あとはプロデューサーとまではいかないですがロサンゼルスで映画ビジネスにまで深く関わっている日本語ができる米人女性弁護士も1人おられますね。でも私の知っている限りでも片手でおさまるレベルで、今回の本題の「ハリウッドの現場でプロデューサーとして活躍する日本人」という観点でいうと、ほとんどいないというのが回答かと思います。
※マシ・オカ(1974~):日本の俳優・プロデューサー。IQ180以上のギフテッドと判定され、6歳のときに母に連れられロサンゼルスに移住。ブラウン大学から1997年にILM社で映画の仕事にエンジニアとして携わり、2006年のテレビ番組 『HEROES/ヒーローズ』 のヒロ・ナカムラ役で有名になる。
――:プロデューサークレジットというのは、DisneyとかWarnerとか映画配給会社の重役になればつくのでしょうか?
そこは日本と違うところで、ハリウッドだと映画配給会社はあくまで「出資者」や「配給者」の立場。実際に制作にかかわらないと、プロデューサー、エグゼクティブ・プロデューサーといったクレジットはつかないですね。やっぱりクリエイティブなプロセスにちょっとでも絡まないとエンドロールには名前を残せないので、実態が伴っていることが多いかと思います。特に映画では、エグゼクティブ・プロデューサーよりもプロデューサーのクレジットの方が中心的に制作に関わったことを示す慣例があるかと思います。
――:弁護士だった中原さんがそこに入れているというのがいかに特別なことであるかが分かりますね。中原さんがクレジットされている作品(制作/開発中作品を含む)は下記になります。今並行して何本の映画及びTV作品に関わられているのでしょうか?
<映画作品>
『Sonic the Hedgehog』 (Paramount、2020) 興収3.19億ドル
『Sonic the Hedgehog 2 』(Paramount、2022) 興収4.05億ドル
『Sonic the Hedgehog 3 』(Paramount、2024) 興収4.92億ドル
『The Angry Birds Movie 3』 (2026)
『Sonic the Hedgehog 4 』(Paramount、2027)
『SHINOBI』(Universal Pictures×サム・ハーブグレイブ監督兼プロデューサー)
『アウトラン』(Universal Pictures×マイケル・ベイ監督兼プロデューサー)
『ハウス・オブ・ザ・デッド』(ポール・アンダーソン監督)
『ベア・ナックル』(Lions Gate×デレク・コルスタッド脚本)
『エターナル・チャンピオンズ』(Skydance)
<TVシリーズ>
『Sonic Prime』(Netflix、2022-)Executive Producer
『Knuckles TV Show』(Paramount+、2023-24)Executive Producer
『ゴールデン・アックス』(CBS) Executive Producer
いまはポテンシャル案件で進めているものも含めると映画とTVを併せて20本弱になりますね。たしかに2020年の『Sonic the Hedgehog』が私のプロデューサーとしてのデビュー戦でしたので、この5-6年で急激に増えました。

▲左から中原徹氏とJoe Chandler氏(代表作「American Dad!」など。TVアニメシリーズ『ゴールデン・アックス』で中原氏と共にエグゼクティブ・プロデューサーをしている)

▲右から中原徹氏とMike McMahan氏(米国コメディ脚本家/プロデューサー、代表作に「Rick and Morty」「Star Trek: Lower Decks」など。同じく『ゴールデン・アックス』でエグゼクティブ・プロデューサーを務めている)
■ミシガン大学のカフェテリアで論争を仕掛けるディベートの悪魔
――:中原さんの生い立ちからお聞きしていきたいです。
1970年生まれで横浜育ち、高校まではずっと日本でした。ただ親が全日空のパイロットだったということもあり、ちょうど自分が大学に入ったころに親がサンフランシスコ勤務になるんですよ。妹は高校からアメリカ暮らしでいわゆる「帰国子女」なのですが、私は違いますね。アメリカにもよく渡航していたこともあり、当時は軽い日常英会話くらいは困らない、くらいのレベルでしたね。
――:そもそもいつから映画の仕事をしようと思っていたんですか?
小さいころから映画とスポーツが大好きだったんですよ。弁護士より前に、映画とスポーツに関わる仕事をしたいなと思っていて、最初にそれを意識したのは中3のときの進路相談でしたね。将来の進路志望書みたいな書面を中3の教室で書かされた時に、教室がうだるような夏の暑さで、「いまごろアラブの石油王は冷房の効いた部屋でクリームソーダを飲みながらポンプが石油を汲み上げるのを見て稼いでいるのか」と思って「石油王」と志望職業を書いたら、担任に「もっと真剣に考えろ」と叱られ、親も謝っていました。その時に、じゃあ大好きな映画とスポーツに関わるにはどんな仕事ができるんだろう、と。
その中3の進路相談で思いついたのが「国際弁護士」でした。思えばそこから高校進学、そして大学は早稲田の法学部に行き司法試験に通って弁護士になる道は、あのタイミングが初めて意識した瞬間でしたね。
――:ロースクールも無い時代です。司法試験は最難関の資格試験で有名でしたね。
いわゆる旧司法試験を24歳の時にクリアして、司法修習のあとに2年間東京の国際法律事務所にいました。東京永和法律事務所というところで、幸い自分の業務時間の半分くらいは目指していたスポーツや映画等のエンタメの世界に関われました。大手広告代理店の仕事が多く、そこでNHL(米国アイスホッケーリーグ)の最初の日本での試合(アナハイム・ダックスVSバンクーバー・カナックス)の契約だったり、“外タレ"のCM契約をやったり、と。そちらは2年弱で退職しています。
――:苦労して弁護士になったのに2年というのはずいぶん早い転機ですね。
日本でスター弁護士と呼ばれる方々にたくさんお目にかかりました。でも、米国の弁護士やビジネスパーソンに相対すると「かみあってない」感じが、衝撃だったんです。英語力やプレゼンテーションの問題なんだと思うのですが、いいようにあしらわれてしまって、アメリカの弁護士たちが一段上に見えたんです。今でいうと高校球児って大谷翔平さんのプレイやたたずまいを一目見たら「こうなりたいな!」って強烈に思うじゃないですか?それが当時の日本の弁護士界では感じられなかった。
日米対決でこんなに歯が立たないんじゃ、自分があこがれていた映画やスポーツの世界で戦っていける弁護士には10年、20年と日本でやっていても無理だなと思ったんです。それで一度日本の弁護士をやめて進路を考えなおしました。ちょうど27歳ぐらいですかね、無職になってアメリカへの渡航を考えました。
――:え、弁護士って4-5年働くとそのまま社費留学みたいなのでアメリカのロースクールか提携事務所いけますよね?それは使わなかったんですか?
もったいないですよね。弁護士としての社費留学も待てなくて、しかも事務所からお金出してもらうと戻って来ないといけないし、日本に一生戻る気もなかったので、若気の至りでいきなり退職しちゃってるんですよ。それで完全自費でミシガン大学のロースクールに入るんです。
――:英語でロースクールというのはかなり大変だったのではないですか?
いや、弁護士の基礎はすでに出来ていますからね。難しいのは法律的なところというより、議論してグループに参加していく部分ですよ。ミシガン大学のロースクールは何百人とアメリカ人がいるなかで、外国人留学生は私も含めて数十人。やっぱり言語的にはビハインドがあるその数十人は「お客さん」のような感じもありますし、その中で固まりがちですよね。
――:ネイティブとの議論勝負って、なかなか太刀打ちできないですよね。
英語がなんとなく通じる、みたいなレベルじゃ全然ダメなんですよ。我々は仕事として「説得して納得させる」という意味での交渉力をあげるための動きをしないといけない。
私は結構「モノマネ」が得意なんですよね。当時HBO等でとにかくアメリカのドラマとかコメディ作品を視聴しまくって、勉強していました。とにかく「楽しい話をする」「相手を笑わせる」ことが大事でした。そうするために実は授業以外で「議論を仕掛ける」工夫をしていました。
――:具体的には何をするんですか?
カフェテリアにおいて、同じ授業を履修している顔だけ見知った人に、突然(ある法的な論点に対する答えである)「A・B・Cの説はどれが正しいと思う?」とディベートを仕掛けるんですよ。あっちも突然声かけられて、「うーん、授業では教授はAだって言ってたけど、私はBだと思う!」という答えに自分は「いや~、Bではないのでは?Cでは?」と(わざと)違う答えを言うところから論戦スタート。次の人はBの論を正統として声をかけて、今度は相手のC論に攻撃を仕掛ける。そんな形で1つのテーマに5人くらいと論戦をくりかえすと、どんな論でもあらゆる立場でディフェンスできるロジックが身に着くんです。しかも、論理的で説得力がある人もいれば、そうでない人もいて、そこから色々なことが学べるのです。これもなけなしのお金をはたいて払っている異常に高額なロースクールの学費の一部なんだなと自分を納得させていました。
――:ナンパでディベートしてるんですね!?。どういうコツがつかめるものなのでしょうか?
ナンパではないですが(笑)。まず「形容詞だけで説得する人」はダメ。やっぱり感情的・情緒的な物言いだけでやることは説得的ではないな、という評価。だからといって全部ロジカルに精密なAIみたいならいいのかというと、それだけで人の気持ちは動かない。途中でジョークを挟んで空気感をつくりながら誘導するほうが、最終的には結果がついてきたりする。ロースクールでの授業は実は半分くらいしかちゃんと出席していなかったんですが、そういうディベートを繰り返していたら、大学でも「あいつはなかなかやるよな」という評価になっていった印象です。
――:すでに日本人離れした肝っ玉ですね(笑)。ロースクール時代は大変じゃなかったですか?
苦労したというより、楽しかったですね。一度日本で弁護士になった後だったけど、小学生に戻ってゼロから学び直すときのような感覚になって、見るもの聞くものすべてが新しかった。
よく大学のカフェテリアでコーヒーを作っていた気さくな従業員の白人のお兄ちゃんがいて、彼ともよく話をしていました。そういう「会話」が、成長機会になるんですよね。彼に「友達の集まりがあるから今度の土曜日に一緒に来ないか」と誘われて行ってみたら、ゴリゴリの左翼系のトラックドライバーたちの集会だったりとか。なまりのすごい英語を聞き取りながら、意外に共和党ばっかりじゃなくて民主党支持っぽい人もいるんだなあとか。マイケル・ムーア監督の出身地だから、彼のファンも多いのでしょうね。
――:まさに「ストリートに飛び込む」タイプですね。
それは弁護士になってからも続いていましたね。事務所でメールデリバリー(郵送物配達)をやっていたアフリカ系アメリカ人の若者らと友達になり、彼が住んでいるLAのサウス・セントラル(韓国系・アフリカ系アメリカ人の暴動になった、LAですごく治安が悪いエリアで、住民はほぼすべてアフリカ系アメリカ人です)に毎週土曜日に通ったり。デリバリーはバイトで、本業はラッパーの集団だったんですよね。彼らから契約の対応も含めて売込みも手伝って欲しいと言われましてね。彼らまだ成功していないから自分の勉強のためにも出世払いで手伝いました。
近隣の場所を舞台にラッパーたちの半生を描いて大ヒットした映画『Straight Outta Compton』(2015)を観ると、描かれているコミュニティ、ファッション、言葉使いなどが本当にそのまんまで懐かしく当時を振り返りました。後に弁護士としてマイク・タイソンやジョー・ジャクソン(マイケル・ジャクソンのお父さん)などと仕事をする機会がありましたが、サウス・セントラルで学んだアフリカ系アメリカ人の話し方や考え方が大きな手助けになったりもしました。「ちょっと違う世界に飛び込む」というのは、昔から好きなんですよね。

▲インタビューを受ける中原徹氏
■ハリウッドの中心に入り込んだ、コメディこそが国境を超える一番の部分
――:ミシガン大学を卒業し、LAの弁護士事務所に入所するんですよね?
はい、修士をとったあとに、2000年にロサンゼルスのピルズベリー(Pillsbury Winthrop Shaw Pittman)法律事務所に入ります。800人の弁護士を擁する、米国でいえばトップ級事務所の一つです。若い新卒が混じる中で、29歳にして私も新米アメリカ弁護士からスタート。そこからヨーイドンで始めて、いわゆるUp or Outの世界です。
――:ずっと不思議なんですが、中原さんって常にマイノリティの選択肢をとりますが、どのくらい他にも同じような道をたどった同僚がいるのでしょうか?
ロースクールではInternationalの学生が確か…30人くらいいて、アメリカに残って弁護士事務所で働いたのは私一人でしたね。ピルズベリーで同じLA事務所に入所の新卒アメリカ人が15人くらいいて…確かに最終的にパートナーまで残ったのも私一人でした。
――:そこに「とんでもなさ」を感じます。ディベート仕掛けるところといい、「マイノリティなのにその世界のセントラルで打ち勝つ」スキルが半端ない。語学力もあるんでしょうけど、そこらへんが“普通じゃない"感じがでてますね。
若い弁護士が法律事務所で成果を出せるかという意味では、いわゆる一般的なサラリーマンと同じですよ。「上司(パートナー)の弁護士やクライアントが何をして欲しいかを読み取り、いかに早くてよいクオリティの成果物を出せるか」ですね。法律家としての基礎力はベースにありますが、それよりも早さとか求められるものを汲み取る能力が必要ですね。いま思えば自分にそれが出来ていたのかよく分かりませんが…
――:結果的に「日本の弁護士が歯がたたなかった理由」みたいなのはわかってくるのでしょうか?
本当の意味での「交渉」ですよね。それはロースクールのカフェテリアでディベートを仕掛けていたときや、LAでの弁護士活動を通じて感じました。アメリカは異人種が集う中で「合理性」「公平性」に重要な価値を置いている。だからこそ論理をべ―スに、ときに人間的な感情論を交えながら相手を説得していく。それに対して日本は基本的には同一人種のなかでハーモニーや調和を大事にする。実は「客観的には不合理・不公平であっても、集団の中で調和が図れるなら、それの方がよい」ということもありうる。法律の世界においても、日本では特に根回しは大事でしたし、交渉のプロセスそのものが違うんだなということに気づきました。
――:ピルズベリー時代も、今のように脚本に関わったりということはあるのですか?
弁護士時代は基本的には弁護士業務だけです。一方、ハリウッドの映画会社にはたくさん弁護士有資格者が勤務していて、主に2つの部局にいます。Business Affairs=ビジネスをまとめるフロントと、ディフェンス側でリスクがないような契約書をきっちりしあげるLegalサイドに明確に分かれています。最初の採用の入り口から、これはBAポジション、これはLegalポジション、と分業されていて、ヘッドハンターからも「今回はBAのポジションだけど興味あるか?」と最初から聞かれますね。
私は弁護士事務所所属の弁護士でしたから、上記Legalサイドのように、クライアントのために契約を交渉・作成する仕事でした。映画は人生のいつの時点でもよく観て来ましたけど、クリエイティブに入っていくのはSEGAグループに入社したあとです。
――:しかしそれでも帰国子女ではない中原さんが10年間ハリウッドのど真ん中で弁護士をやって、今度は日本の原作サイドからプロデューサーになって、というのは夢ある話ですね。
そうですね、教育に携わった期間もありますが、基本的にそれまでの10数年、自分が苦労してきたことがすべて肥やしになっています。カフェテリアでディベートしたり、サウス・セントラル地区に毎週通ったり、映画やドラマも観まくって。一般論ですが、謙虚な日本人は英語を上手く話せないという遠慮も手伝い、挑戦する前から「根拠のない自信のなさ」を持ち、逆にアメリカ人は「根拠のない自信」に溢れています。日本人が英語を香港やシンガポールの人々と同じくらい話せれば、どれだけの人が自信を持ち、挑戦する舞台を広げ、経済力を含めて日本の国力が跳ね上がるのにと思っています。そんなとき、ハリウッドという舞台で、今度はプロデューサーとして挑戦する機会を与えてくださったのがセガサミーでした。2015年のことですね。
■シャンパンタワーのバケツから原作収入をくみ取れ!「ソニック」価値で優位な交渉
――:SEGAグループ入社のときにはどのくらい他の選択肢があったのですか?
2015年の時点で、日米で4社くらいのオファーがありました。弁護士事務所やロサンゼルスの会社など。でもそうしたなかでセガサミーとは、社外取締役をされていた弁護士の先生が私の先輩で、里見治さん(現セガサミー会長)と里見治紀さん(現セガサミー社長)を紹介してくださったのですが、「法務責任者」「IR事業関連」「映画のプロデュース」を3つともやってくれ、と一番魅力的なオファーでした。里見さんらのエンタメビジネスにかける情熱やビジョンに魅かれ、この会社で仕事をしたいです!とお願いしました。

▲『Sonic the Hedgehog2』のプレミア試写会。前列左端が中原徹氏、右手には本プロジェクトの意思決定者であるセガサミー社の里見治会長、里見治紀社長も。
――:どんなふうにSEGAでの仕事が始まるのですか?
最初は東京勤務で、いわゆるGeneral Counsel(企業における法務最高責任者)としてセガサミーグループ内で海外向けに締結している契約のレビューなどをやっていくわけです。その中の一つが、仕掛り案件になっていた(当時は)Sony Pictures/Columbiaとのソニック映画事業でした。まだまともに脚本もできておらず(2014年6月にSony Pictures EntertainmentとSEGAグループ会社のMarza Animation Planetで共同制作が発表された)、そしてそもそもの契約自体もまだまとまっていませんでした。
――:私の知る限り、SEGAでのソニック・ハリウッド映画化は2010年前後の時代から模索されていたと聞きます。
いろいろハリウッド側から提案は来ていたんですが、関係者同士で「これだ!」といえるような脚本になっていなかった。そもそも社内だと「まさか実現なんてしないだろうな」というあきらめのムードすらありました。当時は日本IPのハリウッド映画化に成功例がなくて、皆が横目で見ていた参考事例としては『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』(1993)や『DRAGONBALL EVOLUTION』(2009)でしたからね。
――:原作蹂躙されて、ろくなものにならない、というムードが2010年代は強かったですよね。杉野行雄副社長も「正直、私は反対していました。しかし、結果としてはあの映画があるのとないのでは今のSEGAの業績は全然違ったと思います」と仰っていました(『エンタメビジネスの教科書』2025)
契約も脚本もプロジェクト全体も、まわりで同じような成功タイトルがどんどん出てきて「機運が高まる瞬間」みたいなものがありますよね。今がまさにそうですが、当時はまだそういう時代ではなかった。私も入ってニール・モリッツ※らと一緒に脚本の話を進め、少しずつストーリーを改善していきました。ただ肝心のビジネスがなかなかまとまらない。
私も10年以上ロサンゼルスで弁護士をやってきたからよくわかるんですよ。ハリウッド映画の仕組みって「ホストクラブのシャンパンタワー」なんです。
※ニール・H・モリッツ(Neal H. Moritz, 1959-)、『ワイルド・スピード』シリーズ、『プリズン・ブレイク』など70作以上手掛け、合計120億ドルを超える大ヒット映像を作ってきた。『Sonic』の共同プロデューサーでもある。歴代プロデューサーでも累積興行収入5位に入る、ハリウッドトップ級プロデューサーの1人。
――:え??どういうことですか?
一番上のグラスが溢れると2段目のグラスに注がれるじゃないですか。そうやってどんどんマージンをとられていった上で、下の方の脚本家や端役の俳優などのグラスに売上が注がれるのは一番最後。当時の契約ではSEGAが原作者でありながら、そのシャンパンタワーの一番下の方に位置していて、ほとんど収益にはならないポジションだった。それどころかシャンパンタワーの一番上にはグラスじゃなくて映画会社の「バケツ」が置かれていたんです。
――:なぜそんな不平等契約になってしまっていたんでしょうか?
仕方なかった部分はあります。そんなディールの契約書は日本の弁護士事務所にだってノウハウある人がほとんどいないわけですから。私がまずやったことは「これ、グラスの位置が低いですよ」と警鐘を鳴らすことでした。でもそれが低い位置であることの認識もなく、担当部署も「いやいや、これがハリウッドなんです。これがスタンダードだと言われています」と。そこからは私の出番で、「絶対に契約はブレークさせない。最悪危なくなったら中原がスタンドプレーで交渉したということで切り離してくれてよいので、一度私に話させてほしい」という社内承認を得るところからでした。
2017年に、それまで交渉を続けていたコロンビアとの関係が諸事情により解消され、ゼロからソニック映画を売り込むことになりました。ハリウッドの主要な映画会社にいわば「入札」のように短期間で売込みをかけました。その結果、ビジネス・クリエイティブ両面での基本の考え方が一致したParamountと進めることになりました(2017年10月にParamountがソニックの映画化権取得を発表)。あとは、シャンパンタワーのグラスの位置を最大限高める交渉が待っていました。
――:ハリウッド側からは警戒はされないんですか?いきなり知らない日本人が交渉しかけてきた、と。
私のLA時代の弁護士事務所(ピルズベリー)も現地でよく知られていましたので、スタジオ側の弁護士も、「同じ釜の飯を食った人」という感じで接してきたので、得体の知れない人が来たようには扱われなかったですね。野球に例えれば、元ドジャースでプレーした人が元パドレスの選手に会うみたいな感じですかね。自分なりにピルズベリー事務所で学んだことをすべて活用して交渉に臨みました。
でも最終的に強気に交渉出来て、お互いイーブンの関係に持ち込むことができたのは、私の力でなく、「ソニックの価値」そのものによります。シャンパンタワーの1段目にParamountのグラスがありますが、その下の段くらいの高位にSEGAをもって来られた。そんな条件でもパラマウントはやっぱり組みたいと思うほどにソニックには価値があって、ハリウッドのプロデューサー陣にも高く評価されていた。ソニックってアメリカでは「ドラえもん」並みに認知されていますからね。
■Action、Emotion、Joke。クリエイティブを理解できるプロデューサーに必要な目利き
――:中原さんはどうやってCreativeに口を出せるようになって行くんですか?
2015年にソニック映画案件が自分にアサインされてから、全米でも有名なUSC(南カリフォルニア大学)のフィルムスクール(大学院)で学生が読む基本書を何冊か急いで読みました。つまり、フィルムスクールを出ている映画関係者の基礎教養を自分も身につけておきたかったんですよね。その上で、ソニック映画と関連性のありそうな映画を観まくりましたね。年100本は観ていました。
ブラッドピット主演の『MoneyBall』(2011)方式ですよね。ソニックとジャンルが近そうな映画はとにかく全部観て、見終わったら良いところ悪いところを拾い出す。興行収入やレビューを見て部分的に答え合わせをしつつ、さらにその後ハリウッドのクリエイター達との雑談にまぶして評価を聞く。クライマックスの演出のあそこが秀逸だった、配役が悪かった、ジョークがおもしろくなかった、音楽はよかった、とか。そういう作業を延々繰り返して「自分の中での(ささやかな)ビックデータ」をためていった感じでした。そのうちに、ハリウッドのクリエイター達との会話の精度が上がっていく感触がありました。
――:具体的にはどういう要素がヒット映画の法則、という感じになるのですか?
色々あるのですが、分かりやすいところでいうと、ファミリー向けアクション映画の3要素というものがあります。Action(アクション)とEmotion(感情の機微)、そしてJokeの3つなんです。
――:ジョークというのが意外です。
アメリカンジョークって日本人はあまり笑えないじゃないですか?吉本漫才でアメリカ人が笑えないように。でもそのアメリカンジョークにこそ、アメリカ人が「自分たちの映画だ」と思える要素があるんです。ソニックって宇宙の生物だし、知らない人には得体が知れないじゃないですか?でもそのソニックやその周りの人らが自分達も笑えるジョークを話すことが、「キャラクターとして受け入れられる」過程でもあるんです。ソニック映画の成功の隠れた要因は、私はアメリカンジョークだと思っています。勿論、ジョークのみならず、ソニックに視聴者が親近感を覚えるように、Emotion面で、ソニックが地球で(ビデオゲームでは見られない)泣き言をいったり、弱みを見せたりという工夫もしています。当然のことながら、一番の見せ場であるアクションでは、ゲームのソニックの動きを活かしつつ、ハリウッドのお家芸とも言える派手なアクションを存分に盛り込んでいます。
――:そうか、だからアニメだけど「ハイブリッド」でリアルの人間とソニックが3DCG状態で交流する形にしたのですね。普通のアニメだとアニメキャラ同士の空想的な会話でちょっとシンパシー感じにくいですもんね。
ハイブリッドにしたのはチャレンジでしたけど、だからこそリアルな俳優とのインタラクションで3DCGのソニックの温かい“人間味"が理解されやすくなっていった。
それにソニックもテイルズもナックルズも、最初から全員揃ってしまうとキャラクターごとの思い入れも見分け方もわからなくなる。それで1ではソニック、2でテイルズ、3でナックルズとシリーズごとに中心となる味方キャラが一人ずつ異なる特徴を発揮して仲間入りしていくようにしていく。こういうストーリーテリングがまさにハリウッド側がもたらしてくれたソニック原作への「味」なんですよね。4ではついに女の子エイミーの登場です。
――:ソニックと言えば2019年4月に出したトレイラー(予告編)が「コレジャナイ」と炎上し、作り直しを経て2020年2月公開になりました。あれについてはSEGA側の原作意見が正しかったケースですよね?
ちょっと誤解される部分もあるかもしれませんが、予告編に対してファンが炎上したのも個人的にはある意味で「想定内」だった部分もあります。どういうソニックのデザインが一番よいのか、という議論はずっと続けてきていて、Paramount、ニール・モリッツ、ジェフ・ファウラー(監督)と、SEGAとの間で大きく意見が異なっていた。それに彼らはその世界で何十年も成功していた人たちですからね。なかなか折れない。だったらあちらの主張するデザインをトレイラーに出してみて、上手く行かなかったら修正すればいいと思っていました。
――:じゃあSEGAは反対していたけど、いったんそれでファンの反応をみてみたってことですか?
はい。炎上の大きさは確かに「想定外」で、焦るには焦りましたけど(笑)。でもトレイラーを出す前にすでに制作陣に確認はしていたんですよ。我々に修正する「時間」と「お金」はあるのか?という。
2018年に役者による実写の撮影は終了していましたが、そこと合成する3DCGの部分をどうするか、だけの問題ですからね。それをやり直すだけの時間はありそうだ。そこにかかるお金も、度をこした範囲でなければ大丈夫だ、と。それで2019年に公開したら、ああいった結果になりました。それでSEGAサイドが主張していたビジュアルにしようと一気に転換しました。
※ソニック炎上事件:2016年から映画化が発表されていた中で2018年12月からポスターが少しずつ公開され、ついに2019年4月にリリースされた映像が「原作と全然違う」と大炎上、24時間で1200万再生、高評価17万に対して低評価27万。かたや2019年5月に公開されていた『名探偵ピカチュウ』と比較されて、監督のJeff Fowlerがまさかの「全部キャラクターを作り替える」というその時点で衝撃の意思決定につながる。
――:あの一件はマリオやONE PIECEなど、のちの日本原作IPとハリウッド側の意見調整にも大きく影響したものだったと思います。
仰る通りの重要な一件だったと思います。でも、逆にハリウッド側の意見がたしかに!と思うこともいっぱいありましたよ。先ほどのキャラクターを一人ずつ味方にしていくやり方や、悲しんだり弱みをみせたりする中でEmotionやジョークを挟むやり方だったり。彼らの意見を取り入れることも成功の大きな要素でした。
ここで言いたいのは、SEGA(IPホルダー)側が正しいかハリウッド側が正しいかという議論は意味がないんです。この違う立場と違う経験を持つ多数の人間たちが「お客さんの声を聞き、客観的に分析して、間違いを素直に受け入れ、直せるか」という国境をこえたチームワークづくりこそが大事なんです。
■イコールパートナーでの出資関係、リスクをとれる原作セガサミー
――:ぜひ日本側とハリウッド側でどういうクリエイティブのセンスが違ったのかをお聞きしたいです。まずは中原さんがいつも強調されているジョークですよね。
私としては「ジョークの役割」が、実はActionやEmotionに負けないぐらい大事だと思っています。実はソニックは映画としての成功もそうなんですが、制作チームとしての雰囲気の作り方やそのクリエイティビティの活かし方が特徴的な作品でもあったんです。
色々なシーンで出てくる劇中のジョークの中には、スタッフ同士が休み時間にお互いで言いあったジョークもベースにしたものもあるんです。イケてるジョークがランチ時間に脚本家でも監督でもないスタッフから飛び出したりすると、「ちょっと待って、それ面白い!」となるわけです。その意味でも、上下関係をあまり感じさせない気さくな制作現場の雰囲気は大切だと思います。天才ジム・キャリー(ドクター・ロボトニック役)は抜群のギャグセンスで脚本にどんどん手を入れてくれますが、他のスタッフらのアイデアも貪欲に取り入れる空気がありました。そこはジェフ監督の人柄によるところも大きいと思います。


▲撮影現場での光景
――:たしかにEmotionなどは結構WWEと新日本プロレスでのあおりVなど比較していると結構ストーリーテリングの仕方が日米って全然違うというのも感じます。
そうですね。ソニックから離れますが、私も弁護士時代に格闘技のプロモーターのような仕事をしていたときがありました。米国におけるK-1やDynamite USA!!などの格闘技イベントです。
試合前の選手の「煽りV映像」や番組宣伝のCMにおいて、日本だと人情部分を強調することが結構あるかと思います。家族のために戦う、弱虫だった苦労人が強い選手になったとか。ところがアメリカのTV局は、そういうのは要らないと言うんですよ。お客さんは人情物語に興味はなく、圧倒的なパワー、スピード、技術を見たいんだと。「スピードVSパワー」みたいな分かりやすい切り口で、すごい奴らが激突する!みたいなのがよい、と言って譲らないんですよね。
――:日本だと「狂犬、だけど家族愛」みたいな情緒にフォーカスをあてて、判官びいきっぽいところありますよね。
米国だとスポーツ中継においてはそれでいい、という不文律があるんでしょうね。球場に入る前のリラックスした状態での選手インタビューとか、そういうものも比較的少ない傾向にありますね。プロレスラーの伝記『The Iron Claw』(2023)みたいに、ドラマの部分を見せたかったらそれは完全にそこにフォーカスして映画にすればよくて。でもいちいちスポーツの試合実況でそこまで情緒的にEmotionを強調しない、ということなんでしょうね。
――:「どういうクリエイティブであるべきか」というときに、今回は炎上事件がありましたけど個人的にはそこに中原さんという存在、それに「出資」スキームが大きいと感じています。今回の『Sonic』での画期的な点はSEGA自身も出資している点ですよね。
そうですね、SEGAはParamountと「イコールパートナー」でやってきています。すごい出資だと思います。そこは、会社の経営陣の英断だったと思います。当時の日本で、映画会社でもIP系企業でも、あれほどのディールに自分たちでリスクをとってやったという話はほかに聞きません。
――:鳥嶋和彦さんが2009年の『ドラゴンボール』実写化の失敗を「断るべきだった。断るかお金を積むか、どっちかだった。積むなら50億円、最低ね」と言っています(『ボツ』2025)。中山の知る限り、ちゃんとハリウッド映画に日本企業が出資して入った事例はこの20年、スクウェア・エニックスが130億円の特損を出した『Final Fantasy: The Spirits WithinFF』(2001)以降はないはずです。それを2010年代後半でSEGA自体が決して調子がよいわけでないタイミングでやっているという意思決定が、凄かったと思います。
相当な意思決定でした。AIを使って収支予測をするプロの会社にも頼んで、映画の興行として黒字予測も出しました。こういうシナリオで、ギリギリ失敗してもここまでの損、といった数字を出しながら、かなり慎重に精査をしていきました。
ただ最後は里見治会長が、出すと決めたんですよね。その瞬間、私も「風穴があいた」感じがしました。実際に行くぞと決めた後で『名探偵ピカチュウ』(2019年3月)の公開があり、『Sonic the Hedgehog』(2020年2月)と来て、その後『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(2023年4月)などへとつながっていく。日本IPのハリウッド映画化への機運が出てきた。そういう意味では“最低50億円"の世界に、日本企業として踏み入れた初めての作品と言っていいかもしれません。
■法務最高責任者から映画プロデューサーへ。日本人がハリウッドで活躍する方法
――:中原さんとしてはこの重責のプロジェクトにどう臨んでいったのですか?
拘ったのは、笑われるかも知れませんが、「最低1ドルでもいいので映画自体の収益を黒字にしてやろう」ということですね。もちろん映画が売れれば映画自体の収支は赤字だったとしてもゲームやマーチャンダイジングが相当売れるので副次効果を入れれば黒字、ということになります。でもそういう言い訳なしで、純粋な映画投資として黒字にするんだ、というところには拘りましたね。それがプロデューサーとしての責務ですしね。
ソニックの1作目が成功裡に終わり、ほっとしていたら、2作目以降、さらには、たくさんのSEGAのIPの映像化案件が一気に増加しました。里見治紀セガサミー社長や内海州史SEGA社長らのリーダーシップで、映像化は活発になっています。『ゴールデン・アックス』『SHINOBI』『アウトラン』『ハウス・オブ・ザ・デッド』などなど、SEGAの名作ゲームの映像化が進んでいます。
――:こうなってくると、弁護士としての仕事は減ってくるのですか?
ご存じのようにIR事業は日本のなかでは難しいという判断になりました。General Counselも2020年代に入って映画が忙しくなりすぎて、もう15~20%くらいにまで減ってきた時点で「そろそろ映画に専念してもらった方がいいんじゃないか?」ということで、現在の映画/TV統括プロデューサーという仕事に専念することになりました。ちょうど2022~23年ごろですかね。
――:現在も毎年100本映画を視聴しているのでしょうか?
いま100本はさすがに厳しくなってきて、年70本程度なんですけど、当時よりも担当映画のジャンルも広がったので、ファミリーアクション映画のみならず、アニメ映画、シリアスなアクション映画からホラー映画まで、幅広く観ていますね。
――:まったく違う種類の仕事をどうやって頭で切り替えているんですか?
業務時間は業界人とのコミュニケーションや契約交渉などに充てることが多く、それ以外の早朝・深夜・休日が基本的にはクリエイティブのインプットと脚本を読んで分析する時間です。頭の中のOSを入れ替えないといけないから、クリエイティブはクリエイティブの時間で誰にも邪魔されず集中してやるようにした方がいいかなと思っています。ですから、休みの日に人知れず無精ひげも剃らずに部屋に閉じこもってじっとりねっちり脚本を読んで映像を想起し、空想に耽っていたりしています。
ありがたいことに、アメリカと日本との往来が結構頻繁にあり、日米の関係者とスムーズに意思確認が出来ていますし、SEGAの中でのレポートラインも非常にスリムで、役員として、大人数の大会議に頻繁に出ないといけないということもありません。その時間を、ハリウッド関係者など、対外的な人達と使える現状にあり、この点は会社に本当に感謝しています。他面、日本のSEGA社内で私のことを知っている人は少ないかもしれません(笑)。
――:中原さんのやっていることをいまSEGAが組織でやろうとすると、どういう人が入社してどう育てば、実現するものなのでしょうか?
Business Affairsの方だけみれば、結構いますね。アメリカの弁護士でエンタメを経験している中堅選手を下にいれていけばできるようになると思います。クリエイティブのほうが難しいとは思いますが、LAで普通の若手~中堅の現役映画プロデューサーを見つければ行けるかと思います。ただ、日本語もということになると、いずれの場合も難しいかも知れません。
――:今中山も総務省のプロジェクト委員で映像人材のハリウッド化に関わっていたりするのですが、日本人で中原さんと同じことをやろうとすると、相当難しいんでしょうか?
それは・・・やっぱり言語と文化のハードルでしょうね。Business AffairsであれCreativeであれ、同じ言語を使って、同じ文化で共鳴し合う過程は必須ですからね。そこに普通の日本人スタッフでキャッチアップしていくことはかなり難しいでしょうね。もうかれこれアメリカに住んで合計18年、しかも毎年これだけ映画を観て、実際にプロジェクトもまわして、そうなって初めて「これはハリウッドでウケるかどうか?」みたいなものは少しずつ分かるようにはなってきました。脚本に意見を言っても、受け入れてもらえるようになってきましたから・・・
――:でも日本人以外ではハリウッドで活躍している外国人はいますよね。
スタンダードが違いますよね。イギリス、カナダ、ニュージーランドなどの英語圏は当然ながら、欧州のドイツやフランス、中南米のメキシコやブラジルだって文化面・言語面を微調整だけして入っていける。でも文化も言語も遠いアジア人は大変です。そういう中で特筆すべきなのは韓国人でしょうね。
――:DreamWorks出資から入り込んでいるミキ・リーさんのような事例ですよね。
1997年のIMF管理下時代以降、外需に頼って海外に展開しないと存続できないという危機感のなかでハリウッドにもどんどん飛び込んできた。釜山映画祭(1996~)を始め、韓国の映画関係者が積極的に海外で経験を積んだ。こうした潮流におけるひとつの大きな区切りが、ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』(2019)のアカデミー賞受賞でした。
日本映画やTVシリーズのプレゼンスあがっているとはいっても、やっぱり『イカゲーム』などの韓国映画・TVシリーズのほうが、「欧米人にウケる」という意味ではだいぶ先に行っています。
――:さきほどのEmotionなどの取り込み方もうまいんですかね?
そうですね、やっぱり「作り方の技法」はハリウッド式を取り入れている気がします。例えば、『パラサイト』を初めて観たときに、まずジョークは日本人にはウケないかもしれないけど、アメリカ人にはウケるように作られているなと思いました。映画自体の構成でも、前半は重厚な社会派ドラマかと思いきや、後半はちょっとスプラッターホラー的な移行を見せています。仮に日本で作られたら、終始重厚な社会派ドラマを渋~くまとめるパターンであったかも知れません。
こうした“派手な移行"は欧米で割とウケるんですよ。ポン・ジュノ監督が実際に影響を受けたかは分かりませんが、私はこの移行を見てすぐに、クエンティン・タランティーノ監督の『From Dusk Till Dawn 』(1996)を思い出しました。あの映画でも、途中ガラッと映画が変わるんですよね。『パラサイト』は、米国で評価されるべくして評価されたと感じました。
――:BTSの北米市場への展開もセンセーショナルでした。
サッカーの話になりますが、そもそも奥寺康彦氏の時代から、海外に渡航してチャレンジしている選手の数は韓国人のほうが母数も多かった気がします。映像の世界でも一足先に『パラサイト』などが展開されています。この10-20年で韓国のプロデューサーやクリエイターが続々とハリウッドに出て行く様は「日本人のJリーガーが海外リーグに挑戦しはじめたころ」「日本人野球選手がメジャーリーグで活躍し出しているとき」を彷彿とさせます。
日々欧米の最高のステージで一緒にプレイしているからこそ、いちいち外国の舞台や外国の対戦相手に気後れすることなく、よいパフォーマンスができるみたいなことかなって思います。
――:なるほど、クリエイターの世界でもメジャーリーグ、プレミアリーグでも活動した経験のある日本人選手を創っていかないといけないですよね。
そうなんです。そういう「海外育ち」の母数を増やしていかないといけない。
ただ一方で、そういう文脈と全く違うところで『ゴジラ-1.0』が物凄い評価をハリウッドで受けるという嬉しいニュースが飛び込んできたり、『鬼滅の刃』(特に2025年の無限城編)がしっかりとハリウッドで売れている点は日本の凄いところでもあるんですよね。むしろ1/10以下の製作費であれだけの高いクオリティの映像を創れて(ゴジラの山崎貴監督は尊敬して止まない大好きな監督です!!)、逆に日本のほうがアメリカよりもいいビジネスモデルなんじゃないかという考え方もありますよね。なんでもかんでもメジャーリーガーにすればいいというわけでもない。
――:そうなんです。日本のコンテンツも絶対的によいポジションにはあるんですよね。韓国と攻め方が違うだけで。
Netflixの日本アニメに対する貢献は大きいですよね。ボタン一つで見放題、字幕も吹き替えも見られるし、ファンのすそ野を圧倒的に広げました。コロナによる巣ごもりも結果的にはアシストしましたよね。日本IPにポテンシャルは強く感じます。漫画はタカラの山ですし。いまアメリカで物心つくタイミングからNetflixを観ている子供や若者達には中長期的にすごく好影響が出てくると思います。
ただ、どこかで「希少価値があってクールだった日本アニメがありきたりになり、新しいテイストの非日本アニメが面白い」というような分岐点が来るかも知れないリスクには備えておいた方がよいと思います。日本ではそこまで知られていないけれど日本のストーリーを米国風に作ったNetflixアニメ『Blue Eye Samurai』(2023)はこっちで高く評価されている。『Arcane』(2021~24)や『K-POP Demon Hunters』(2025)もそうですが、ちょっとクールなアートスタイルを取り入れたり、斬新なストーリーにトライしたりと、非日本産のアニメも流行り始めている。日本では理解されていない新しい作風のアニメが一世を風靡してくると、似たようなパターンの日本アニメが飽きられるかもしれない。
――:貪欲に取り入れる、入り込むというのはもっともっとやらないといけない。でも逆にいま上手くいっているドメスティックだがユニークなものは残していかないといけない、ということですね。
色々な意見がありますが、プロデューサーって結局「多くの人たちが観たいものを創る」仕事なんだと思います。時々刻々と人が求めるものは変わるので、安住のない試行錯誤の連続なのだと思います。
映画の撮影現場では毎日約150人のスタッフが働いています。そう思うと自分ができることって本当に限られていると思います。でも、こうした貴重なチャンスを与えてくれたセガサミーや、ソニックを初めとするIPを作り上げてきたスタッフやファンに深く感謝しつつ、視聴者が存分に楽しめる映像を少しでも多く世に出す仕事を続けられたら嬉しいなと思います。

会社情報
- 会社名
- 株式会社セガ
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 代表取締役会長CEO 里見 治紀/代表取締役社長執行役員COO 内海 州史/代表取締役副社長執行役員Co-COO 杉野 行雄
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1916億7800万円、営業利益175億3900万円、経常利益171億9000万円、最終利益114億8800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Re entertainment
- 設立
- 2021年7月
- 代表者
- 中山淳雄
- 直近業績
- エンタメ社会学者の中山淳雄氏が海外&事業家&研究者として追求してきた経験をもとに“エンターテイメントの再現性追求”を支援するコンサルティング事業を展開している。
- 上場区分
- 未上場