【インタビュー】『誰ガ為のアルケミスト』&『ファントム オブ キル』シナリオチームに訊く…オリジナルな“人間ドラマ”を生み出す手法とは

2017年1月28日で、リリースより1周年を迎えた、Fuji&gumi Gamesの『誰ガ為のアルケミスト』。
本作は、7人の主人公が織り成す壮大でドラマティックなストーリーと高度な戦略性に富んだ「三次元空間戦略バトル」が楽しめる、本格的タクティクス大作RPG。キャラクターが選べるジョブは80種類以上に及び、緊迫感に満ちた3Dマップでのバトルを堪能できる。
今回は、gumi Westのアベンジャーズ(関連記事)、『誰ガ為のアルケミスト』プロデューサー&ディレクター(関連記事)に続き、シナリオの中核を支える作家陣にインタビューを実施。本作のエグゼクティブプロデューサーであるFuji&gumi Games(以下、FgG)の今泉潤氏、フリーランスの作家である日高勝郎氏を始め、gumiの齋藤詩織氏、松本崇明氏、中岡史郎氏の5人に、『誰ガ為のアルケミスト』(以下、『タガタメ』)や『ファントム オブ キル』(以下、『ファンキル』)の物語がどのようにして作られているかお話を伺ってきた。
■物語の基盤を支えるのは“作家性×整合性”

▲写真左から、日高勝郎氏、今泉潤氏、齋藤詩織氏、中岡史郎氏、松本崇明氏。
──:まず始めに、日高さんを始め、シナリオチームの面々はどのような体制で業務にあたられているのでしょうか。
今泉潤氏(以下、今泉):フリーランスの作家である日高さんが、メイン作家になります。齋藤、松本、中岡が弊社の人間で、日高さんから送られてきた原稿をチェックすると共に、ときには自らシナリオを執筆することもあります。
齋藤詩織氏(以下、齋藤):ライターよりは”編集者”という表現の方が近いかもしれません。
――:今泉さんと日高さんが出会われたきっかけは何だったのでしょうか?
今泉:日高さんのことは、僕がテレビドラマを制作していた頃から知っているので、今で8年ほどの付き合いになりますね。実は、日高さんの作家デビューのきっかけは僕なんです。
日高勝郎氏(以下、日高):僕の作家歴のスタートですね。当時、所属していたプロダクションから「役者のオーディション」と聞いて現場に行ったのですが、何故か書く側にまわされて「どういうことだ!?」と。しかも、既に出演者もキャスティング済みという状況でした(笑)。
そこから、作家を続けるうちに本を書く面白さに気付き始めたんです。役者は、与えられた台詞と設定の中で自分なりにどう料理し、その世界に馴染んでいくかの勝負なのですが、作家には、世界観から全て自分で作れるという楽しさがありました。
──:お二人が『タガタメ』を一緒に作ることになった経緯はいかがでしょうか。
今泉:実は、GREEで展開していたブラウザゲーム『任侠道』をリリースした頃から一緒に仕事をしています。当時は、僕も新人プロデューサーだったので、ざっくばらんにお話できる新人の方に脚本を頼みたいということで日高さんに依頼しました。日高さんは、作家を始める前から俳優業を兼任されていることもあり、脚本の台詞が非常に魅力的です。
──:日高さんは、『タガタメ』ではどういったところを担当されているのでしょうか。
日高:本編の1、2章や、イベント「聖石の追憶」などのシナリオになります。ちなみに、「聖石の追憶」は、『ドラゴンジェネシス -聖戦の絆-』の「聖石の記憶」イベントを『タガタメ』流にアレンジしようというところが発端となっています。また、『ファンキル』では天上編メインシナリオ全てを担当しています。

──:そこに、齋藤さん、松本さん、中岡さんはどのような形で関わられているのでしょうか。
齋藤:私は、『タガタメ』をメインに担当しています。作家さんからいただいたシナリオを確認し、世界観との整合性が取れているかをチェックするのが主な仕事です。ほかには、武器やアイテムの名称、説明文を作成しています。キャラクターの設定や台本、文章や文字が関わるものは全て携わっていますね。
今泉:キャラクターがそれぞれどの時代に生きていたかといった情報管理や、設定資料集的な部分を担ってもらっています。世界観の土台を守る人というイメージです。僕らが忘れてしまったときに「あの場面でこんなこと言ってなかったっけ?」と質問すれば、「このイベントでこういうことを述べています」と的確に返してくれますね。また、複数の作家にシナリオを任せることでいろいろと齟齬も発生することもあるため、そういった点において如何に本編とリンクさせるかというタクトを振ってくれています。
──:物語の整合性を保つために気を付けていることはありますか?
齋藤:まずは全てのシナリオを把握していなければいけません。キャラひとつとっても、どのキャラがどのシーンに登場しているかしっかりと時系列を作り、ここでこれをしたら20年後に何が起きるといった年表を社内用の資料として作っています。
――:管理するにも膨大な量になりそうですね。
齋藤:はい、ひたすら年表に書き出し、常に見返せるように自分の手元でどんどんと打ち込んでいきます。あとは自分の記憶頼りなところもあるので、忘れてしまわないようによくメモを取っています。
今泉:複数の作家陣が書いているものを読み比べ、「何章でこのキャラがこのように述べているので、この設定は無理です」というキーパーを担ってくれています。
日高:自分の書いた台詞のひとつが、これまでの全てに引っ掛かったりすることもありますからね。
齋藤:キャラの感情が時系列的に繋がらないときには、作家さん用にそのキャラが出てくるシーンを資料化したりもしています。世界観を守っていくことと、広げていくことが大事です。

──:なるほど。松本さん、中岡さんはいかがでしょうか?
松本崇明氏(以下、松本):ざっくり言ってしまうと、僕は、齋藤が『タガタメ』で行っている業務を『ファンキル』で担当しています。
中岡史郎氏(以下、中岡):僕も『ファンキル』の担当です。松本の補佐をしながら、過去にシナリオライティングをしていた経験を活かして執筆にも少し携わっています。
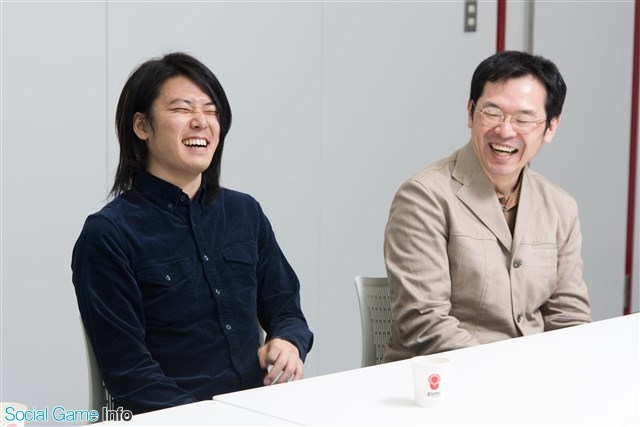
――:作業の流れとしてはどのように進行されているのでしょうか。
齋藤:発注が来たら、まずは自分の手元で制作したものをチームのトップに見てもらい、今泉に提出して良いかを確認します。そうすることで、チーム内でのクオリティを保っているのですが、プロデューサーチェックの段階でNGになるものも多いですね。
今泉:一般的な制作現場と比べると、僕は凄くうるさい方だと思います。スキルの名称ひとつ取っても、自分が発してみて気持ち良くないと嫌なんですよね。
齋藤:ときには、ひとつもスキルの名称が決まらない日もありますね。「5文字じゃない」「もっと漢字を入れたい」といった意見を受けながら延々とやり取りをしていたり、最後の1文字が決まらないという状態から、良さそうな組み合わせの漢字をどんどん送り付けたこともあります。
今泉:あと、整合性に関しては齋藤が担保してくれているので、イラスト発信の企画も多いです。具体的には、『ファンキル』のセブンスキラーズがその例ですね。ファーストキラーズの対になるキャラを作りたいという案から、イラストチームが描き上げたものと、テキストチームが文章に落とし込んだものを組み合わせ、どうやってストーリーに絡めるかを考えるといった作り方をしています。
──:シナリオを作る大きな流れとしては『タガタメ』も『ファンキル』も同様でしょうか?
 今泉:基本的には同じです。まず始めに僕が大まかなプロットを書いたうえで日高さんと話し合い、どういったキャラを登場させるか検討します。そこでは、「とにかくこんなイメージでやりたい」という風呂敷を広げていきます。そのうえで、整合性を取っていくのが僕の仕事で、キャラの台詞や世界観といったメインストーリーの縦軸を伸ばしていくのが日高さんの役割です。その中で設定からズレたときに指摘をくれるのが3人の役割になります。
今泉:基本的には同じです。まず始めに僕が大まかなプロットを書いたうえで日高さんと話し合い、どういったキャラを登場させるか検討します。そこでは、「とにかくこんなイメージでやりたい」という風呂敷を広げていきます。そのうえで、整合性を取っていくのが僕の仕事で、キャラの台詞や世界観といったメインストーリーの縦軸を伸ばしていくのが日高さんの役割です。その中で設定からズレたときに指摘をくれるのが3人の役割になります。──:制作において苦労された部分はございますか?
日高:ゲームのフォーマットにこだわらないという点で苦労しました。あまりゲームということを意識せず、ドラマ本編を作るような感覚で作っているものが、ゲームになっているのが凄いと思っていただけるような、アプローチの仕方をしたいと考えています。
今泉:無理に型にはめようとして、無難になりすぎてはいけないので、ゲームのフォーマットには僕が合わせますとお伝えしているんです。「何話にまとめてください」といった限定的な依頼ではなく、面白く、良いシナリオを作るためなら自由に書いていいよと。
──:自由に、というのもまた難しいお題ではあると思うのですが、執筆にあたって日高さんなりのコツはあるのでしょうか?
日高:役者出身であることを活かし、登場キャラ全てに対して役作りをしています。そうして話しているうちに、”この人がどうなったら物語が展開するか”、”笑ったりショックを受けたりするか”、そして、”それを見たときにどう感じるか”を紡ぎながら、最初に設定した目標地点と合致させていきます。主観と俯瞰を並行させているイメージですね。
今泉:言いやすいように台詞を自分で口に出しているというのは、いかにも役者ならではだという感じがします。発するうえで、違和感なくすっと台詞が入ってくるという点に関しては、FgGの作品全体を通して大切にしている部分でもあります。
■芯を貫くからこそ横に広がるFgGの制作スタイル
──:『ファンキル』と『タガタメ』で異なるポイントはあるのでしょうか?
日高:『ファンキル』の場合は、最初から「天上編」と「地上編」という構想がありましたので、何かの拍子で地上に生きている人たちが天上に行くところが見られるという設定が自分の中にありました。さらに、ファンタジーの世界観に突然紛れ込んでしまった人が、その環境に置かれたときどう感じるかというフレッシュさを入れたいと思っていました。
逆に、『タガタメ』の場合は、中世の騎士として、しっかりとその場で生きている感覚を入れたかったんです。例えば、日本の時代劇を見ると、出来事自体は昔の話ですが、演じている役者たちは本当にそこで生きているような感覚がありますよね。『タガタメ』の1章では、その感覚を同じように再現できればと思いました。また、近代的な2章は僕が得手とするところです。一昔前の機械の国、スチームパンクのイメージがすぐに湧き、そこからは物語が走るように書きあがっていきましたね。
『ファンキル』は真っ白なところから産み出していく感覚に近いですが、『タガタメ』は既にあるイメージの中に入り込んで作り上げるという感覚の違いが僕の中にあります。
今泉:アプローチとしては、『ファンキル』の天上編は主人公が喋らないので主観になっています。その場合、ドラマをやろうとすると決断が主人公に委ねられず、周りに頼ることになるので話の展開が遅くなります。壮大な世界や戦う宿命を描くという意味では、両作ともに日高さんに縦軸を担っていただいている点で共通しているのですが、『ファンキル』の経験を踏まえて、『タガタメ』では主人公を作ろうという話になりました。ただ、途中で飽きてしまわないように主人公は変えていきたい。そこで、主人公が7人いるという企画からスタートしたわけです。縦軸のメッセージ性として、『誰ガ為のアルケミスト』というのは、誰のための力なのか、この力をどう使うのかを主人公7人に背負わせていくというのが土台になっています。

──:主人公が変わることによる描きやすさはいかがですか?
日高:新鮮な気持ちになります。1章の主人公が2章で登場した際に違う側面が見られて、また新しい魅力が見えたりすると面白いですよね。イメージとしては、短編をたくさん作っている感じです。
今泉:立体的なものが最後にまとまっていくRPGのワクワク感がありますよね。『ファンキル』では戦わなければいけない女の子の宿命を描き、一方『タガタメ』では錬金術を何のために使うのかを切り口として人間ドラマを描いています。予定調和で悪者を決めて対立させるようなことはしたくないので、1章に登場するサバレタやガビロンドにも彼らなりの正義があるんです。
──:御社のタイトルはどれもテーマがブレることなく筋が通っていると感じます。
松本:決まった枠の中で如何に自由にできるかを志していて、その枠を逸脱しないからこそ軸を通して進めるのだと思います。
例えば、『ファンキル』で萌えの要素を強く押し出した「ファンキル学園」というイベントを開催したのですが、これもシリアスな本編がしっかりと確立されているからこそ、萌えがより際立つ結果となりました。なので、軸を通したうえで何かをするというのが、僕らの仕事として根付いている部分ではあります。

今泉:ファンキル学園については、松本が入社した頃に「好きにやれ」と命じました。感情が高まると暴走するという設定の骨子は変えずに、如何に世界観で変えられるか。殺伐としていない彼女たちの側面を、ストーリーとして見せられるかに現場で挑戦してみてほしいなと。ファンキル学園の中で描かれている彼女たちの成長やストーリーについてはチェックしましたが、基本的には彼らに任せる形で制作を進めました。
松本:イベントに出演させたいキャラの候補を絞ってから今泉に提出するのですが、その過程でも「このキャラのこういうシーンが見たい!」という煩悩をチームでぶつけ合いましたね。
今泉:ファンキル学園をきっかけに、今では現場発信型のコンテンツも増えてきています。
──:ファンキル学園というイベントを通じて、具体的にはどういった経験を得られたのでしょうか?
松本: 学園ものだからと言って“ただ萌えさせればいいわけではない”とユーザーが何を求めているのか、主観だけでなく俯瞰することが身に付きました。また、どうすれば客観性が生まれ、ドラマが生まれるのかということを通して学びました。
中岡:同じ話でも、僕らで相談してまとめたものを提出したときに「今、見せるべきはここだ」という視点を変えることを教えていただきました。実際、視点を変えてみると面白くなるという気付きや学びがあったのが良いことだと思います。
今泉:ファンタジーの世界なら、いろいろなことを超越して現実ではあり得ないことを実現できますし、それを通すことでまた違った感情を生み出すことができるのではないかという話はしていますね。現実では耳触りの悪いような事象も、ファンタジーのフィルターを通すことで広げることができるんです。
例えば、『タガタメ』3章では女尊男卑の世界が描かれているのですが、そういった舞台設定の中で、果たして男たちはどういう気持ちになるかを表現しています。そして、その根底には人間の感情があって、そこに共感できるかどうか、物語を読んだユーザーが「こういう状況になったらこう思うんだ」と感じられることが面白さに繋がるのだと思います。これは、ファンタジー且つオリジナルタイトルだからこそできる僕らの武器です。

──:そういった感情の動きを表現するための工夫はどういったことで行われているのでしょうか。
今泉:台詞についてはやはり作家性ですね。例えば、3章や4章は日高さん以外の方に執筆をしていただいたのですが、そこで作家同士の化学反応みたいなものが起こるのではないかと考えています。あとは、システムとのシナジーとしてバトル時の連携スキルにもこだわっていますね。このキャラとこのキャラが連携したらカッコいいよね、というところから逆算してシナリオを考え、そこからさらに広げていくという進め方です。ゲームシステムとしてワクワクする感覚を如何にシナリオに組み込むかという点については、柔軟性も必要ですね。量や時間が限られている中にどれだけの想いを込められるか。具体例として挙げられるのは、『ファンキル』と『魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボですね。ワルプルギスの夜は、まどかとほむらの連携スキルで倒した方が絶対盛り上がるというところから、親密度を上げることで使えるようにしました。物語とゲーム性がリンクする部分を作ると、ゲームに一層の奥行きが出てきます。
■シナリオ制作における”やりがい”と”意義”
──:ゲームにおけるシナリオについてはどのようにお考えですか?
日高:作家からすると、何でも書けるという特徴はあります。テレビや映画では、シチュエーションやスケジュール、季節でNGが出ることがありますので。また、極論を言うと、ゲームが許してくれるなら、蟻の目線になったり、火星に行くこともできます。何でもできるからこそ、自分が何をしたいかという意思が必要です。
今泉:僕はゲームにおいてもドラマを描きたいという考えのもと制作しています。シナリオは手紙のようなものだと考えていて、例えば、僕が感謝を伝える手紙を見せたときに自分の母親は感動すると思うのですが、僕のことを知らない人が、僕らが作ったメッセージを読んで感動してもらえるような仕事はエンターテインメントにしかないと思うんです。ただ、それは等身大の僕が言葉として伝えるのではなく、『タガタメ』のロギという少年を通すことでより印象的なメッセージとして投げかけることができます。そうすることで、僕らの手紙を素直に受け入れられるようになるのがストーリーだと思います。どんなメッセージも人が受け取らなければ日記で終わってしまうので、誰かの人生に影響を与えられるようなことを続けていかなければいけませんね。
プロデューサーの仕事が何かということを考えたときに、最後に残るのは価値観だと思います。監督や作家の作品をお客様と引き合わせ、ひとつの価値を生み出すのがプロデューサーの役割ですよね。

──:皆さんは、どういったところにやりがいを感じていますか?
齋藤:俗物的な話になってしまいますが、自分の作った台本を声優さんに読んでもらえるというのは嬉しいですね。
松本:自分たちの作ったオリジナル作品が話題になることが、やりがいを感じられる瞬間だと思います。
中岡:何かを作り上げた瞬間に自分で良いものができたと思えればやりがいを感じますし、作ったものを他の仲間と突き合わせることでより面白いものになれば最高です。さらに、ユーザーから「面白い」と言われると次への活力にもなりますね。
――:御社ならではの特徴を教えてください。
松本:プロデューサーとこれほど話せる会社はないですね。
中岡:これほどチェックが厳しいところはないですよね(笑)。
松本:厳しいですが、接する時間は長い。
中岡:指摘も的確で「確かに!」と納得できるからこそ、しっかりと修正することができます。今泉さんは、提出したものをちゃんと隅々まで見てくれますし、本当に芯がブレないです。
齋藤:”面白いものをリリースする”というゴールだけが決まっていて、そこにたどり着く手段については問われないという空気感はあります。オリジナルタイトルだからこそ、いろいろなことを試せますし、プロデューサーと密に話せるからこそ、より深い部分を模索していける面白さがあります。もし、この業界でやりたいことができないと感じている方がおられたら、弊社の環境はピッタリだと思います。

──:現在、チームとしてこういった人材を採用したいという理想はございますか?
松本:何かしらの形で尖っている人が良いと思います。
中岡:他人からは尖っていると言われるけど、自分ではその自覚がない人。
今泉:日常で映画や漫画、小説といったエンタメに触れる機会が多く、それを主観だけでなく客観で見られる方は貴重ですね。
──:ちなみに、みなさんはどういった職を経て御社に入社されたのでしょうか?
松本:僕は雑誌の編集をしていました。多種多様なジャンルに携わってきまして、その経験を今、活かすことができていると思います。
中岡:僕は小説やゲームシナリオの制作など、ライティングをしていました。
齋藤:私は漫画の編集プロダクションに在籍していた時期が長かったのと、全く別の業種でマニュアルを制作する会社にいたこともありました。
今泉:今も『タガタメ』のマニュアルを作っていますからね。
齋藤:確かにそうかもしれません(笑)。編集プロダクションでは、PR記事を制作したり、漫画の入稿をしたり、コンテンツを世に送り出すお手伝いをしていました。
──:資格やスキルといったものはいかがでしょうか?
今泉:資格というわけではないですが、どういう風に物語が作られていくかに興味がある人で、コミュニケーション能力が高い人だと良いですね。

──:最後に、今後の展望についてお聞かせください。
中岡:脚本でも企画でも、笑える話で人を面白がらせられるものを作っていきたいですね。
松本:僕らの作ったものを見て感動してもらえるような、人の感情を揺さぶれるものを作っていければ良いなと思っています。
齋藤:私も、ユーザーに楽しんでいただけるものを送り出し続けたいです。最初に作ったキャラがリリースされて、とあるユーザーがそのキャラを気に入って毎日SNSで推してくださっているのを見たとき、本当に嬉しかったんです。自分が携わったものを明日の活力にしてくれる人を増やしていきたいです。
日高:僕は理想として、こうして作ったものが媒体を超えて、アニメやドラマ、映画になると良いなと思っています。現状、放送されているドラマにも物量や深さ、費やした時間で負けていない感覚がありますし、もっと世の中に広まってほしいという夢があります。
シナリオとしては、次はもっとミニマムな世界、下町の町内会からスタートして世界に広がっていくような話が書いてみたいですね。
今泉:映像を手掛けていた頃からの夢なのですが、僕はエンタメの頂点であるハリウッド映画を作りたいです。GREEやmobageでゲームを作った当時、50万ダウンロードを達成して、モバイルゲームは力のある媒体だと感じました。その中で映像化するならドラマだという話から、ドラマを描き、映像にもしたいという視点で制作を進めてきたので、日高さんと同じく媒体を越えたいという想いはあります。
2016年のエンタメ業界を見返すと、『シン・ゴジラ』や『君の名は。』など、自分たちが信じたものをやり続けた結果、ヒットに繋がっているのだなと感じます。そのことから、大事なのは継続性だと思っておりますので、ハリウッド映画を作りたいという夢を抱きつつ、まずは現役を続けていくことですね。そのためには、作品単位で守らなければいけない部分を守り続け、面白いもの、飽きないものを織り交ぜていくことが大事なのではないかと思います。
――:本日はありがとうございました。
(取材・文:編集部 山岡広樹)
(撮影:TAESOO KANG)
(撮影:TAESOO KANG)
■『誰ガ為のアルケミスト(タガタメ)』
© Fuji&gumi Games, Inc. All Rights Reserved.
会社情報
- 会社名
- 株式会社gumi
- 設立
- 2007年6月
- 代表者
- 川本 寛之
- 決算期
- 4月
- 直近業績
- 売上高89億4200万円、営業利益3億7000万円、経常利益21億300万円、最終利益20億6300万円(2025年4月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3903
会社情報
- 会社名
- 株式会社Fuji&gumi Games
- 設立
- 2014年1月






