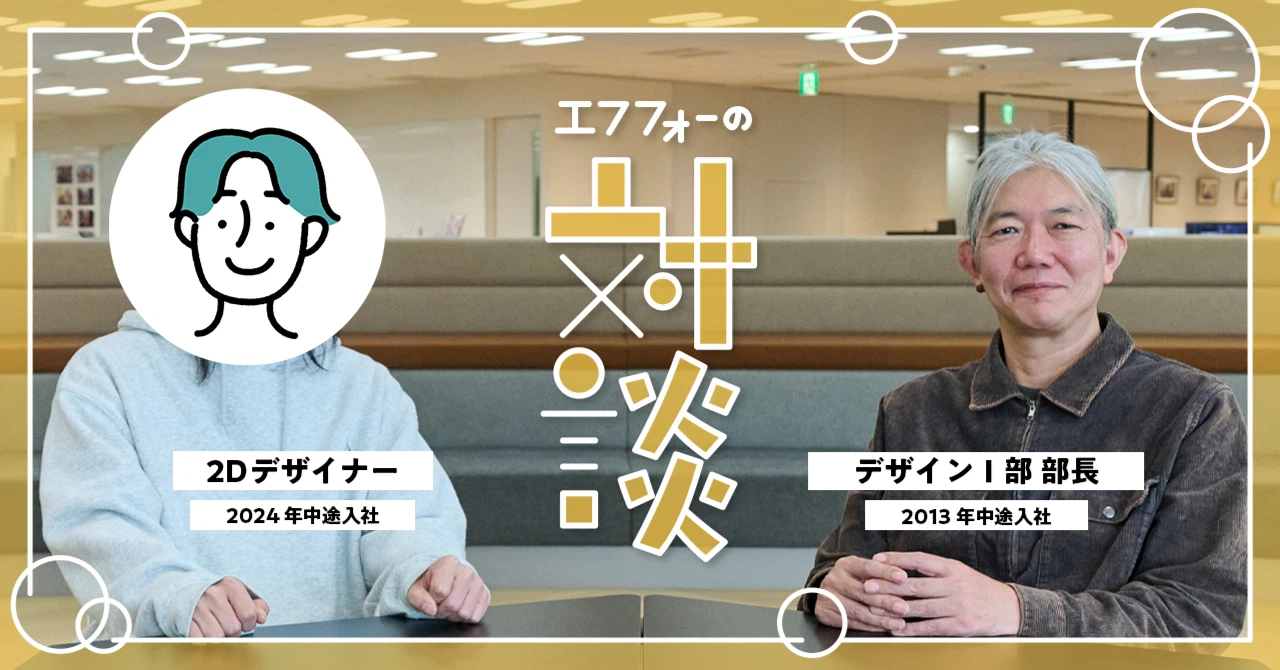スマートフォンゲームにて多くの人気作を手掛けるアカツキゲームス。「Whyを込めたゲームで世界の人々の感情をつなげる」をミッションに掲げ、作品の世界観を表現豊かに描いている。
2017年にリリースされ、5周年を迎えた『八月のシンデレラナイン』(以下、『ハチナイ』)についても、キャラクターたちの青春模様をリアルに描いており、多くのユーザーから共感を得ている。
ゲームでは、シナリオによる世界観やキャラクターの表現も重要となり、多くのシナリオライターによって生み出されているが、アカツキゲームスのシナリオ制作では、チームとして制作することを大事にしているそうだ。
今回はそんなアカツキゲームスシナリオチームに座談会インタビューを実施。5周年を迎えた『ハチナイ』の振り返りやシナリオ制作の手法、アカツキゲームスのシナリオチームならではの特色について語っていただいた。
シナリオの積み重ねが花を開いた5年間の『ハチナイ』

株式会社アカツキゲームス
『八月のシンデレラナイン』シナリオチーム
(写真右から)
チームリーダー
大竹直紀氏
シナリオライター
泉 遼平氏
シナリオディレクター
植木誉人氏
長谷川隼也氏
――:『ハチナイ』が5周年を迎えましたが、振り返ってみて、印象に残っているシナリオはありますか。
大竹:僕は今年の球春祭ですね。
今回のシナリオでは大きく2つのペアにフォーカスを当てていました。岩城良美という本校の選手と、対戦する小河原高校の鬼塚桐のストーリー。そしてもう一方が、こちらも本校の坂上芽衣と、同じく小河原の樫野亜沙という、それぞれが特別な関係値があるなかで描かれるドラマです。
かつ、大会のシナリオなので試合としてのドラマも描き、本校35人のメンバーの思いも描くなど、色々な要素をそれこそ2年以上前から描かれてきたものも含めて、ああいった形にできたということに感慨深さがあります。
長谷川:言われてみれば、一つのシナリオの中に3つのテーマを同時並行しながら、いかに偏らせず読ませるか、読了感を持たせるかをまとめあげたんですよね。
植木:前後編と分かれていたので、バランスよく描くのを意識していたと思います。
見せ場となる描写やドラマ要素を、読み進める中でちゃんと楽しめるような工夫を行いました。
実際、シナリオを書いてくださったライターさんが一番パワーを使ったと思うんですよね。
泉:テーマが複数混ざっている中、それを全部ゴールに持っていくというシナリオだったので、誰が書いても苦労するだろうなと当時思いました(笑)。
ただ、実際、終わってみれば、『ハチナイ』というタイトルの重さ、普通のエンタメで避けがちなところと真正面から向き合って、描けたんじゃないかと思います。
書いているときは辛かろうが、作品が出来上がって、それを楽しんでもらえれば全部報われますよね。ライターはそういう生き物なんだと思います。
長谷川:僕はちょっと視点を変えて、あえてメインシナリオ以外で挙げようと思います。
『ハチナイ』にはいろんなシナリオがあり、例えば選手ごとの誕生日を祝う誕生日シナリオやタウンマップでの会話劇があります。
5タップぐらいで終わる会話劇もあったりして、それこそ毎年あるバレンタインやクリスマス、各選手の誕生日とかに作られるシナリオも細かく作り込んでいます。
バレンタインなどでは、プレゼントを渡したりもらったりする趣旨ですが、それをいかに35人分、差別化して、この選手はどういう風にプレゼントを渡してくれるか。渡したら喜んでくれるのかを考えるのを、ライターさんと一緒に擦り合わせながら進めて行ったのも印象に残っています。
実際、監督さんごとに推し選手の反応を楽しんでいただいて、SNSとかにあげていただき、「すごい嬉しかった」という声見たときは本当にやっていてよかったなと思いますね。
植木:あれ、うれしいですよね。スクショも撮ってくださって、ここの台詞が好きみたいな感じでSNSにあげてくださるじゃないですか。こちらも見ていてうれしいなって気持ちになります。
泉:僕は花山栄美という選手の『あの子と結んだ約束』というシナリオが、一番印象に残っていますね。
このシナリオは、あるライターさんが書いてくれた内容をもとにしており、チーム全体として大事にしている「ハチナイイズム」が受け継がれているなと実感できた話でした。
花山栄美という恋愛に憧れている子が野球を頑張る話なんですが、当初、雑談混じりでそのライターさんが構想の種を話していたんです。
実際に描いたのはまた別のライターさんだったんですが、イベントがリリースされた際に、監督さんからものすごく反響がありました。
誰かから誰かへと、バトンのように受け取ったものをちゃんと形にできたという意味で、印象に残っているシナリオです。
植木:今の、すごく良い話ですね。
仕事って、俯瞰的に見ると、依頼されてそれをこなすという関係だけになってしまうことが多いじゃないですか。
でも、今の泉さんの話の根底って、関わっている人の顔が浮かんでいますよね。
あの人はどういう気持で作ったんだろう?と、想像して、じゃあアウトプットはこうすると監督さんは喜んでくださるんじゃないだろうか?って、いろんなところに顔が浮かぶのはすごく良い仕事だなって感じました。

僕が印象に残っているのは向月高校の選手、岸楓佳が初めてリリースされたイベント「ふたりの在り方」というシナリオですね。
岸は高坂椿という気難しい性格をしたエースとバッテリーを組んでいて。そんな気難しさに難儀する岸がどうして高坂の女房役になっているのか、どういう想いでその子の球を受けているのか、深ぼるような内容です。
そのシナリオ自体、非常に反響があったんですけど、その後、夏大会の岸楓佳と高坂がバッテリーとして王者界皇高校に臨むのですが、そこに繋がるドラマとしても盛り上がる要素が非常に多かったので、1番好きなシナリオと言えます。
先ほど、泉さんの話の中にバトンを受け取ったとありましたが、まさしくこの岸という選手を描くときにも同じことが起きていましたね。
過去に各ライターさんが撒いていた種を見つめ直し、リリースするタイミングでまた別の担当ライターさんが種を育て、積み重ねた結果のもとに開花したんだなと感じます。
長谷川:『ハチナイ』のシナリオチームでは、「この選手はこのライターさん担当」といった完全分業制にしていません。
基本的には全ての形態のシナリオ執筆に携わっていただくようにはしています。
なので、植木さんが例に挙げたように、複数のライターさんによってその選手が積み上がっていき、世に出ていくということもあります。
植木:その背景って、僕はいつも思うんですけど、やっぱり「一緒に作っていこうよ」という感覚から生まれますよね。僕自身、アカツキのすごく良いところだと思っています。みんなで育てているんだぞという気概があるというか。
もちろん、完全分業制によって効率化が図れる良さもあります。ただ、効率化から外れた部分に、みんなで育んでいくぞとか、その“育む”という言葉が抽象的であるがゆえに、可能性の広がりがあるんだと思います。
そこには多分、作品としての面白さが潜んでいて、たとえば泉さんではないライターさんがそれを探し当て、さらに泉さんがそれをキャッチアップすると何が生まれるんだろうか、といった楽しみがあるんじゃないかなと思います。
大竹:それはその通りだと思っていて、事前に資料として作られた設定は、設定でしかありません。
実際はシナリオの一つ一つの台詞などで紡がれていくことによって、その選手たちの物語が生み出されていきます。それらすべてを1人だけで書くことは難しいです。
まさに今、そういったところが植木さんの言うとおり、みんなで作っていく。実際に具体化していくことになるんじゃないかなと思います。
チームで話し合いながら作っていくアカツキゲームスシナリオチーム
――:シナリオチームにおいて、アカツキゲームスならではと思う部分はありますか。
泉:僕はもう10年以上、フリーランスでシナリオライターをやらせていただいてますが、これまでの職場では、案件ごとの契約というか、シナリオを書いて作品が出たらおしまい、といった形態が多かったです。
ですから、運営型のゲームに関わること自体がアカツキで初めてで、結果的に今までで一番長く携わらせていただいているんですが、チームとしてシナリオを作ることに重きを置いてくれているのが、アカツキの良い点だと思います。

話し合いの場が多く設けられ、意見交換がすごく積極的に行われています。各々が抱いている面白さと面白さがぶつかり合って、時には議論が白熱することもあるんですけど、基本的には、お互いの意見を尊重しようという姿勢が皆さんから感じられます。
あくまで自分の場合は、ですが、熱意の根底に作品を良くしたいっていう思いがあれば、面白さの方向性がいろいろ違ったとしても、やっぱり根っこの部分で信じられると思います。
作品に対する思いとか、作品を良くしたいという想いを相手から感じることで、相手を信じる姿勢を持ちたい、という気持ちになれるのかもしれないです。
植木:ライターさんは皆、本当に『ハチナイ』を大事にしていると感じます。それこそ、この後の『ハチナイ』をどういうふうに描こうかも含めて、『ハチナイ』が好きという根底があると感じます。
皆さんの良くしていこうという想いがあるからこそ、僕も同じ熱量を持つことができて、これが信頼関係なのかなと思います。
あとは、そもそも意見を出し合う場をアカツキゲームスでは大事にしています。社内全体で共通認識的に持っているので、シナリオチーム外とも話し合うことを大事にしており、意見を出し合うことには慣れるような環境だと言えます。
これは持論ですが、チームは遠慮し合わない関係がいいと思っています。ただ、お互いに敬意がなければ議論はただの喧嘩になってしまうので、配慮する気持ちは必要です。ハチナイのシナリオチームにはそういった根底があると思います。
大竹:いろんな事例があると思いますが、チームも大規模になればなるほど、その人の役割は固まってきますし、コミュニケーションも減ってくるとは思います。それこそ、場合によっては本当に機械的に与えられたものをこなすといったスタイルも多いと思います。アカツキゲームスでは、ちょっと違って、常にリンクしながら作っていくのが特徴かなと思いますね。
植木:「ハチナイとは何か?」という疑問を常に意識して、チームで話し合ってますよね。
長谷川:「ハチナイイズム」みたいなことはよく言いますよね。
中々言語化できていない部分もありますけども、チームとして話し合っていく中で、積み上がっていく文化みたいな。
植木:めちゃくちゃ分かります。基本的な概念として、シナリオ制作は“起承転結”などの構成論があって作られるものじゃないですか。
ですから、面白さはある一定まではロジックでどうにかなってしまう面もあると言えます。
ただ、「ハチナイイズム」という言葉の中で大事にしてきた思想に触れないと、それ以上のものにならないと思います。
チームで受け継がれていく「ハチナイイズム」
植木:「ハチナイイズム」というと、現在執筆中の部分もありますが、夏大会シナリオの描き方が鋭くなってきていますよね。
今、『ハチナイ』の世界では、トーナメント形式で夏大会が進行していますけど、決勝に近づけば近づくほど、敗者に対してのカタルシスや、勝者が次の強者へ臨むという挑戦、といったエンタメとなる要素が多くなってきていると思います。
他の皆さんが、どこを大事に描いていたかというのは改めて聞いてみたいです。
泉:自分は、やっぱり『八月のシンデレラナイン』の青春体験を一番大事にしています。
その中で、”青春”って何だろうと考えたときに、時間制限が一つの要素として挙がります。
チームに加わってすぐの頃は、3年間の高校生活という区切りに対する意識がすごく強かったです。
ですから当初、結構過激な意見を内に抱えていて、本当の意味で青春体験をしてもらうのであれば、3年間でサービスを終わらせるべきだと密かに思っていました(笑)。
ただ、運営型のゲームは長く続けば続くほど愛される時間も長くなります。その分、魅力も色んな人に知ってもらえますし、感情も分かち合えるので、今は納得しています。それでいうと、夏大会を何年もかけてじっくり描くという方針も、最初は躊躇がありましたね。
長谷川:スポーツマンガやアニメ作品だと、一つの試合に何週もかけて描きますよね。だから、1試合終わるのに、いつの間にか1年かかっていたということもありますが、運営型ゲームのシナリオにおいても似た作り方になっているのかなと思います。
大竹:それについては、ただ長く引き伸ばして描いていくという訳ではなく、より丁寧に描いたり、物語を広げることに僕らは力を使ってきたのかなと思います。
そして、少しずつ時間が進むことによって、そこで広げた伏線やドラマがまた一つに収束していく、という部分にも面白さを感じて欲しいなと思いますね。
泉:本当に週刊連載のようなスタイルだと思います。物語の大きな方針はあっても、結末にたどり着くまでを丁寧に描く必要性が生じたときに、その中で何ができるのか?というのは、今までの仕事だとなかなかないことでした。
決められた締切に向けて、決められた文量を書く、みたいな仕事しか知らなかったので、新しい考え方が身についたと思います。
長谷川:でも実際、『八月のシンデレラナイン』は週刊連載って言葉がぴったりなのかなと思っています。その難しさも、チームに入って初めて実感しましたし、5年以上も連載しているのはすごいことをやっているチームなのだと感じます。
植木:年月かけていけばかけていくほど、環境も変わっていくじゃないですか。そのときに、「ハチナイイズム」のような共通の意思がどれだけ紡がれているのかは、チームにおいてはすごく大事なんでしょうね。
これまで積み上げてきた文化や、これからも大事にしたい青春体験というキーワードを真面目にその時代に合わせて考えていくことが、多分、このチームの根底にはあるんだろうという気がしています。
――:お話を聞いていると、皆さん自身も青春体験をしているなと感じますね。
長谷川:青春体験というと、結局、自分の経験を投影していることも多いので、そうかもしれません(笑)。
僕自身は、学生の頃、野球はやっていませんでしたが、同じ運動部としても、どういうのが一番青春体験としてはまるんだろうかと考えることはありますね。
植木:考えますね。だから、青春体験は甘くないぞという考えあるじゃないですか。つまり、苦い経験もあるということ。
泉:それは確かに大事でしょうね。このシナリオチームでも大事にしていますよね。
長谷川:ただキラキラしているだけではなくて、言ってしまえば負の面というか、苦い思い出、黒歴史にしたくなるような体験とかも多分あるはずなんですよ。悔しい思いとか。嫉妬心とか。

植木:陰りの部分ですよね、本来は語りたくもないような。でもハチナイはそこも含めて描こうとしてますよね。
エンタメの世界での、女の子を扱う作品は、基本的に陰りの部分を避けることが多いと思います。『ハチナイ』のシナリオ表現においては、青春というものに紐づいた場合に、リアリティを考えると、やっぱそういう一面もあるよねとプロデューサーからGOサインが出ることがあります。
泉:自分は、スポーツに興味を持ったのがJリーグ全盛期で、親に「サッカーやりたい!」と言ったら「野球やれ!」と返されて、高校まで野球をやる羽目になりました(笑)結果的に『ハチナイ』と出会えたことはすごい幸運なことでした。
長谷川:そうなんだ(笑)。
泉:なんとか9人揃うような少年野球チームに入れられて、毎日のように負けては練習の繰り返し…。
中学も高校も、正直良い思い出より、つらい思い出のほうが多いです。
その頃からゲームや読書が好きだったので、部活動に十分に努力はできなかった学生時代でした。
ただ、それが今、すごく『ハチナイ』に生かされているんじゃないかなと思っています。
あの時、本気で物事に取り組んでこなかったんだから、今回は頑張ろうという気持ちはあります。似たような生い立ちの選手には感情移入しちゃいますね。
「おまえは頑張れ!俺のようにはなるな!」みたいな気持ちが込もっているかもしれない(笑)。今となっては、野球を勧めてくれた親にも感謝しています(笑)。
植木:まさしく青春ですね(笑)。僕自身の話でいうと、青春時代キラキラした思い出はありません。振り返ってみると、いわゆる反抗期と言えるような家族を疎ましく思っていた時期でした。
なんであの時、コミュニケーションを取らなかったんだろうかという自省が今になってあります。
そういう鬱屈したときの自分を忘れられないでいるから、鬱屈した子たちを描くときにも、その理由が何となく分かる立場でいられるのだと思います。
――:5年以上も続けていると、産みの苦しみとかもあるのではないでしょうか。
泉:アカツキのシナリオチームに入る以前は、発注されたものを受けてただ書くことしかやっていませんでした。ですが、ここではライターひとりひとりが、より深くシナリオについて考えながら書くことがシナリオ班の仕事でした。
一つの話としてまとまりがあって、自分では面白いと思っていても、その先につながる種が何もなかったりすると、それはここでは100点にはならないんだなというのは、新鮮に感じたものです。
大竹:そして必ずしも、種を撒いた本人が、その続きを書けるわけではないという(笑)。
長谷川:その種が花開いて、別のライターさんが収穫してくれるというのは、泉さんはどのくらい想像できているんですか?
泉:緻密に計算はしてないです。なんとなくこんな花が咲いたらいいな、くらいのもので(笑)。
自分から見たときに、この芽は伸びなそうだなというものがあったとしても、他の方から見たときに面白い発想が出てきそうであれば、是非ともそれを活かしてほしいですし、それこそがチームの強みなんだと、今改めて思いましたね。
大竹:チームのみんなは多分、土壌が分かっていると思うんですよ。『ハチナイ』だと「ハチナイイズム」という土壌が。

この種を撒いていても大丈夫だろうという感じでやっているのかもしれない。そこがアスファルトだったら、種を置いても意味ないじゃないですか。
だから多分、育つだろうという空気は感じてくれているんだろうなと思います。
植木:『ハチナイ』では、陰りと言えるような種も許される作品というのが強いんじゃないかと思うんです。
いわゆる、美少女が登場する作品は、キラキラしたところを描きたいはずなのに、『ハチナイ』では、陰りとか悔しい気持ちなどの負の部分も描くようにしているから、想いも継承されているのかなと思いますね。
泉:植木さんのいう通り、キャラクターをキャラクターのままで終わらせないようにしていますよね。
キャラクターじゃなくて、ちゃんと1人の人間を描くんだぞとなると、植木さんが言った陰りの面もたくさん見えてきます。
植木:よく人間としてどうなのかと、キャラクターとしてどうなのかという、それぞれの視点で物事を考えることがあります。
そして、シナリオチームで会話しているときは、人間の方の話をしているなと感じることが多いです。
泉:その人間らしいリアルさと、キャラクターならではのフィクションさが程よく混ざっているのが、『ハチナイ』ならではの魅力だと思います。
植木:可能な限り、ライターさんには、人間のほうを考えてもらいたいと思いますね。
例えば、キャラクターとして売りをつくるとか、あるいは今後、売れっ子になるかどうかみたいな目線もあると思います。
ただその考え方は、シナリオディレクターが持っていればいいんじゃないかなという気はしています。
多分、その目線だけで泉さんと話をすると、ただ喧嘩するだけになるかもしれません。もちろん、キャラクターとしての売りを忘れちゃいけないんですけど、でも、その意向とかを、シナリオチームとして可能な限り実現するためにはどうすればいいんだろうという相談を僕はここで一緒にしたいですね。
大竹:まさにそういったところを考えてくれるのが植木さんの役割であり、大きな力になっています。
ライターさんは、それぞれ、その時々で一番面白いと思えるシナリオを作ることに全力を注ぐ。そして、プロデューサーが示す方向と依頼とのバランス取りは、シナリオディレクターの方々に担っていただくというような感じです。
泉:実際、植木さんが言ってくださったとおり、「人間らしさ」を考えることに専念させてもらうことで、シナリオチームは人間要素を存分に描かせてもらっていますし、シナリオ以外の部分でキャラクター要素の魅力を出してもらっていたりしています。
植木:長所を存分に生かしてもらい、最終的にバランスが取れればいいなと。
アートチームなど、他チームの得意としているところも生かしていき、全体で作品を作り上げていく。そして最終的に、監督さんに面白いと思っていただく。この積み重ねが『ハチナイ』が5年も続けられた理由でもあるのかなと思います。
これからも青春体験を追いかけて

――:今後の展望や描きたいものについてお聞かせください。
泉:僕からはやはり、1年目からずっと一緒に、ライターという視点から共に歩んできた有原たちが、今では2年目の夏を、決勝戦という一番大きな舞台を迎えようとしていることに感慨深く感じます。
先ほどの話題にもあったように、僕らも青春体験をしているんだと思っています。クリエイターとしても成長させてもらった意識がありますし、本当に、有原たちと一緒に自分も成長してきた自覚があります。
だからこそ、最後まで一緒に走り抜けたいなという思いでいます。もちろん、サービス自体はまだまだ続くので、引き続き楽しみにしていただきたいです。
長谷川:僕も同じ気持ちですね。2年目の夏大会というのをこれまでずっと1年、2年かけて描いてきた中で、その決勝戦がいよいよ今年の夏でお披露目されます。
その後の展開、夏大会が終わった後に、一体彼女たちがどういう風になっていくのか。
物語がどのように動いていくのかは鋭意制作中なので、そこも含めて監督さんには今後、しっかりお届けしていきたいなと思っています。
大竹:2年目の夏大会での決勝戦が、今年の夏の大きな目玉になるわけですが、それは同時に、一般的には3年生が引退を迎えるという時期でもあります。そういう意味では、つらい部分もあると思います。
ただ、そのつらさもちゃんと表現していく作品であり続けるんだというのは大事にしていきたいですし、やっぱり青春体験という言葉を使っている作品なので、シナリオとしてもキラキラした部分や陰りの部分の両方を含めて、しっかり描いていきたいですね。
――:最後に読者に向けて一言お願いできますか。
大竹:チーム全体という目線でお話しすると、本当に、『ハチナイ』はドラマ性を重視して、日々シナリオを作っています。
シナリオチームに限ったことではありませんが、チームには色々なバックボーンを持ったライターさんやクリエイターさんがいます。
その中で、『ハチナイ』のシナリオチームは、ドラマを作るという観点おいて、一芸を持った方たちが集まったチームだと思っています。
ですから僕は、チームが力を発揮できるようにサポートしていきたいなと思っていますし、単純に大きな目線でいうと、「アカツキゲームスのシナリオ、面白いね」って言われるようになりたいですね。
長谷川:大竹さんからもあったように、『八月のシンデレラナイン』では、ひとつのシナリオに対しても、多くの方々が関わっています。
そして何より、監督さんの声にもきちんと耳を傾けて作り出していくことも大事だと思っています。
これからも監督さん含めた多くの方々と一緒に『ハチナイ』の青春体験を描いていきたいので引き続きよろしくお願いします。
泉:以前は、ファン感謝祭みたいなイベントとして、実際に監督さんに会社に来ていただいたり、直接お会いする機会も作っていたんです。
今は感染症の影響もあって、中々実現できていませんが、当時監督さんが付箋に描いてくださった応援コメントは今もオフィスにあり、僕たちの励みになっています。
また、ああいった機会も作っていきたいので、これからもよろしくお願いします。
植木:『ハチナイ』を通じてアカツキゲームスのシナリオチームや、シナリオを作るお仕事に興味を持ってもらえたらうれしいなと思っています。
それに見合うだけの物語を『ハチナイ』で描けたらと思いますので、ぜひ注目いただければありがたいです。

――:ありがとうございました。
(撮影:SYN.PRODUCT)
■アカツキゲームスのオウンドメディア
■『八月のシンデレラナイン』
会社情報
- 会社名
- 株式会社アカツキ
- 設立
- 2010年6月
- 代表者
- 代表取締役CEO 香田 哲朗
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高236億5200万円、営業利益39億1500万円、経常利益42億3300万円、最終利益16億4600万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3932